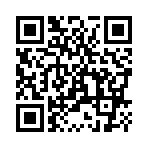2008年01月30日
サッシを入れる
長野市川合新田で工事が進むKさんの家

今日は、大工のマキオさんがリビングのサッシと窓を入れているところに
立ち会いました。
まず、サッシの中心に棒をあてがってもちあげ、所定の位置に据えます。
さすが大工さん、上下の行き来も
たいへん軽やかです。。
サッシを施工したら、家の奥のほうに置いてあった窓を運んできます。
これがかなりの重さなのだそう。
そこで手伝いを申し出ましたが、「腰の骨折られても困るからなあ(笑)」と
丁重にお断り。。
背中に窓をひとつずつ背負って、窓際まで運んだマキオさん。
その方法だと、重たいものでもけっこういけるのだそうです。
滞りなく窓を設置し終えました

ちなみに現在のK邸の様子ですが、天井はすでにプラスターボードが張られ、
そして、階段がすでにできあがっています。
2Fはこのような状態です。
床のコンパネと天井のプラスターボードが張られ、サッシもすでに設置済み。
この風景がどう変わっていくのか、今後もどうぞお楽しみに。
2008年01月29日
善光寺前の藤木庵さん、内部造作工事が進んでいます
善光寺前で工事が進む、蕎麦処『藤木庵』さん

先月の建前から1ヶ月以上が経過した今日の様子です。
中央通りのほうから見た外観はこんなかんじ。
建物自体は、白いビニールシートですっぽりと覆われているため、今はまだ
全体の雰囲気がつかめません。。
裏口から入ると、まず設備屋さんが作業をしていました。
すでに硬質ウレタンによる断熱材の施工は終わっていて、壁一面が淡いグリーン色。
建物が広く、短期間で多くの作業が必要になることから、棟梁のトシミさんを
はじめ、何人もの大工さんたちが入って作業しています。
さて、中央通りに面した入口から入った場合、正面になるのがこちら。
若手大工さんが、そば打ち場の天井のプラスターボードを施工しています。
玄関とお食事の場所をつなぐ、天井の高い廊下。
その廊下部分で、窓枠の寸法を測っているのが、棟梁のトシミさん。
中央通りからどんなふうに見えるのか、今から
気になるところです。
せっかくなので、かかっているはしごをのぼって、
2Fへ上がってみました。
下をのぞくと、善光寺木遣り歌の師範でもある大工のアライさんと、
藤木庵の現場代理人のクボさんがなにやら打ち合わせ中の様子。
2F、廊下上の天井の際には、正方形の明かりとり用窓が整然と並んでいます。
2Fに配されたお食事場所。
どのような雰囲気になるのか、この状態を見ただけではまだ想像がつきません。。
この空間は、すでに壁までプラスターボードが施工済み。
現場には、これから施工される予定の建材や棚用の板、材木がたくさん
積まれていました。
春のリニューアルオープンへ向けて、まだまだ大工さんたちの忙しい
日々が続きます

2008年01月24日
県庁近くの平屋建て、でき上がりの様子をHPにアップしました
12月中旬にお引渡しした県庁近くのKさんの家。
その様子を、当社ホームページの一般住宅施工例 にアップしました!
お施主さんは、30歳代の若夫婦です。
大胆な表わしの梁や火打ちが印象的なリビング・ダイニング。
Kさんが「120点のでき」と大満足のテレビ台の枠と、その上の壁面収納は、
K邸を手がけたヤマモト大工さんの手作りです。
新居を訪ねてきた家族やお友だちからは、
「別荘みたい」
「玄関に入ってすぐに暖かい」
「リビングがすごく居心地がよくて、自分の家にいるみたい」
「木の感じがいい」
などなど、とても好評で、なにより、お施主さん自身が「いろんな人に見てほしい」
と思う家になったとのこと。
実際、木の色の使い方、部屋の配し方、造りつけ棚のバリエーションなど、
参考になる点がたくさんあるお住まいです。
施工例でかなり詳しくご紹介してありますので、みなさまぜひ一度ご覧ください

2008年01月23日
稲里にて、上棟しました
稲里で新築予定のS邸、上棟前日

ほれぼれするように美しい刻みっぷり。。
ために加工された突起部分)が作れるのは、
手刻みならでは、です。
ひさびさ、営業アライさんの植物シリーズが出てきました...
「なんですか、この恐竜の足先みたいなのは」
「わからないかなァー、まだ硬く閉じてふくらまない木の芽で、"寒さ"を表現したんだよ」
...ということで、"大寒"翌日の昨日、無事S邸が上棟しました

車の通りが多い交差点近くが建築現場のため、道路側に木っ端やナットなどが
飛び出さないよう、防護ネットを張っての作業です。
昨日も大勢の大工さんたちが応援にかけつけていました。
気の知れた大工仲間同士、手際よく構造材を組み上げていきます。
上にのぼって掛け矢をふるっているマキオさん、上棟のときは、この役回りが
多い様子。
ヤマナカさん、そしていっしょに作業する
のが写真右奥のキウチさんです。
現場には、傷がつかないよう緩衝材できっちりくるまれた構造材がたくさん
置かれていました。
「"磨き"がたくさんあってたいへんだったよー」と棟梁のヤマナカさん。
この材が、室内空間でどんな風に生きてくるのか、今後注目です

面積も広く、家の木組みも少々複雑なSさんの家。
1F部分の作業の組み立てがひと段落したのは、お昼をずいぶん回ってからでした。
このとき大工さんたちは、お昼休憩中。
点々と置き去られたヘルメットが、抜け殻のよう。。
そして夕方17時前。だいぶ姿が見えてきました。
上棟作業も大詰めです。
待っている間の寒さを紛らわすために竹箒で
掃除していたところ、まんまとアライさんに
撮られてしまいました。。
帰社後のアライメモには、
「ウラノさんの弟子も寒い中頑張っていました」。
弟子、って...
上棟式がはじまりました。
それぞれ塩・米・酒をもって、家の四隅を
祓い清めます。
みんなでお神酒で乾杯。
そのあと今日も、上棟を祝う善光寺木遣り歌が、
建ったばかりの家に響き渡りました。
上棟式を終えて。
無事に上棟し、ヤマナカさんとウラノさんが、どことなくほっとした様子で
歓談していました。
構造が組み上がった家を見渡して、「こうやって見ると、ほんとうに木をたくさん
使ってるってことがわかりますねえ」とSさん。
具体的に住まいの姿が見えてきたことで、新しい家ができるという実感が
心の奥からふつふつと沸いてこられたようです。
Sさんの奥さんは、「歌(木遣り)を聞いて、なんだか感動しました」とのこと。
ご夫婦の感激されている様子に、こちらもうれしいきもちになりました。。
"紫陽花(あじさい)の咲く頃"の完成を目指し、工事は進められます

2008年01月19日
気密測定の様子
朝、出社すると、机の上に"アライメモ"が置かれていました。

...スクープって...そしてこの"目と眉毛シール"はいったい何...
 じつは今までもときおり、メモに
じつは今までもときおり、メモに
これらの目・眉毛・口シールが貼られて
いたことが。
どうやら、いろいろなバリエーションが
あるらしい。
しかしまあいったいどこでこんなシールを
手にいれたのでしょう。。
それはともかく、今日の話題は、気密測定。
家の中で感じられる身体的な快適さは、暖かい・寒いといった温熱環境に
大きく影響を受けています。
温熱環境をよくするためには、断熱性や気密性を高めることが必要で、
とくに高断熱・高気密住宅ではその気密性能を数値で実証するために、
必ず、気密測定を行います。
その気密測定を、会社からもほど近い南高田のTさんの家で行う、というので
Tさんの家のプランニングを担当した設計士のセトさんと二人、会社の白い
ママチャリを漕いで現場に向かいました

到着したときは、設計士のワダさんと代理人のウラノさんが測定装置のセッティング中。
気密測定は本来、家が完成してから行われることが多いのですが、
壁をすべて完全に覆ってからでは、万が一、測定値が基準に満たない
場合に原因の場所を特定し手直しすることがむずかしいため、
鎌倉材木店では構造を完全に覆う前に測定しています。
気密測定の装置は、送風機・流量測定器・屋内外の圧力測定器・屋内外の温度計
などで構成されます。
上の写真に写っているのは、送風機。
窓やドアをすべて閉め切って屋内を密閉状態にし、この送風機で住宅の中と外との
圧力差をつくります。そして空気の圧力差と流量を測定。
グラフを作成し、それをもとに隙間相当面積(C値)を算出します。
隙間相当面積(C値)というのは、床面積1㎡あたりにどのくらいの隙間が
あるかを表す数値。
よってこの数値が小さいほど、隙間がない性能の高い住宅、ということになります。
そして気密性が高い分、24時間換気システムで、きっちりと空気の出入りを管理
することが大切になります。

気密測定士の資格をもつワダさんが設定しているシルバー色の箱型機械が、
さまざまな機能が詰めこまれた測定器本体。

大工さんたちは、普段どおりに作業をしていました。ヤマグチさんは、ドア枠を施工中。

わたしが2Fに上がって、
 「ここがトイレになる予定の場所で」、
「ここがトイレになる予定の場所で」、
 「ここが洗面台の置かれるスペースで...」、
「ここが洗面台の置かれるスペースで...」、
などと写真を撮っている間に

測定終了。
セトさんが数値を読み上げて、ワダさんがパソコンでデータを確認をしています。
検査は、一発OK
最低でもC値は1.0以下が望ましいとされますが、T邸の結果はその数値を
ばっちりクリアしていました

...スクープって...そしてこの"目と眉毛シール"はいったい何...
これらの目・眉毛・口シールが貼られて
いたことが。
どうやら、いろいろなバリエーションが
あるらしい。
しかしまあいったいどこでこんなシールを
手にいれたのでしょう。。
それはともかく、今日の話題は、気密測定。
家の中で感じられる身体的な快適さは、暖かい・寒いといった温熱環境に
大きく影響を受けています。
温熱環境をよくするためには、断熱性や気密性を高めることが必要で、
とくに高断熱・高気密住宅ではその気密性能を数値で実証するために、
必ず、気密測定を行います。
その気密測定を、会社からもほど近い南高田のTさんの家で行う、というので
Tさんの家のプランニングを担当した設計士のセトさんと二人、会社の白い
ママチャリを漕いで現場に向かいました

到着したときは、設計士のワダさんと代理人のウラノさんが測定装置のセッティング中。
気密測定は本来、家が完成してから行われることが多いのですが、
壁をすべて完全に覆ってからでは、万が一、測定値が基準に満たない
場合に原因の場所を特定し手直しすることがむずかしいため、
鎌倉材木店では構造を完全に覆う前に測定しています。
気密測定の装置は、送風機・流量測定器・屋内外の圧力測定器・屋内外の温度計
などで構成されます。
上の写真に写っているのは、送風機。
窓やドアをすべて閉め切って屋内を密閉状態にし、この送風機で住宅の中と外との
圧力差をつくります。そして空気の圧力差と流量を測定。
グラフを作成し、それをもとに隙間相当面積(C値)を算出します。
隙間相当面積(C値)というのは、床面積1㎡あたりにどのくらいの隙間が
あるかを表す数値。
よってこの数値が小さいほど、隙間がない性能の高い住宅、ということになります。
そして気密性が高い分、24時間換気システムで、きっちりと空気の出入りを管理
することが大切になります。
気密測定士の資格をもつワダさんが設定しているシルバー色の箱型機械が、
さまざまな機能が詰めこまれた測定器本体。
大工さんたちは、普段どおりに作業をしていました。ヤマグチさんは、ドア枠を施工中。
わたしが2Fに上がって、
などと写真を撮っている間に
測定終了。
セトさんが数値を読み上げて、ワダさんがパソコンでデータを確認をしています。
検査は、一発OK

最低でもC値は1.0以下が望ましいとされますが、T邸の結果はその数値を
ばっちりクリアしていました

2008年01月17日
若里の家の、ここ1ヶ月の現場の様子(+ハトとスズメの距離感)
昨年12月10日に上棟した若里のKさんの家。
今日はK邸の、ここ1ヶ月の現場の様子をお伝えします
2007年12月21日(金)

上棟から一週間と半分をすぎた頃。
「北からの風で雪が中に吹き込んで、大変だったんだよ(ここの棟梁の
トクタケさん談)」ということで、ガラ(外壁下地板)を打つ前にとりあえず、
タイベック(外装下地用の透湿・防水シート)で壁を覆ってありました。

このときの内観は、

こんなかんじ。

施工される予定の樹脂サッシがすでに搬入されていました。
 鬼無里から通っているトクタケさんは、
鬼無里から通っているトクタケさんは、
本仕事に取りかかる前に、明け方降り
積もった足場の雪をせっせと掃いてらっ
しゃいました。
2008年1月9日(水)

年末年始明けの9日に現場を訪ねると、ガラの施工がだいぶ終わっていました。

そして、玄関には注連縄が。
どうやら、休みに入ってからお施主さんが来て飾ってくださった様子。
新しく建てている家への想いが伝わってくるようで、うれしいかんじがします

この日トクタケさんは、屋根近くの壁のガラを打っていました。

ガラが打たれると、内観の印象もけっこう変わります。

すでにサッシがはめ込まれていました。
大工仕事は、いちおうの作業工程はあるものの、順序として「こうでなけ
ればならない」という決まりはなくて、現場の条件や大工さんのやりやすさ、
慣れなどによって進め方はまちまちです。
ただ、冬の間、現場は吹きっさらしで非常に寒いため、どの大工さんも
サッシはなるべく早めに入れるよう。
 屋内の一隅には、床用の断熱材がうずたかく
屋内の一隅には、床用の断熱材がうずたかく
積まれていました。
2008年1月17日(木)

そしてこれが、今朝の様子。またしても雪景色です


トクタケ大工さんがいなかったので、中に入ることができず、せめてもと
庭のほうへ回ってみました
少しずつ家らしくなってきている感があります。
 「せっかく来たのに中が撮れなくてざんねん」と思いながらふと隣の駐車場を見やると、鳥たちが群れていました。
「せっかく来たのに中が撮れなくてざんねん」と思いながらふと隣の駐車場を見やると、鳥たちが群れていました。
FLYING RAT(空飛ぶねずみ)とも称されるハトたちが、砂利の間にあるらしい何かをついばんでいます。
そしてそれを遠巻きにみつめるスズメたちの群れ...
 そのまま観察していると、スズメたちがすこしずつハトたちの輪の中に近寄ってきて、お互い干渉することもなく、いっしょに何かをついばみはじめました。なんとなく不思議な異種交流(?)です。
そのまま観察していると、スズメたちがすこしずつハトたちの輪の中に近寄ってきて、お互い干渉することもなく、いっしょに何かをついばみはじめました。なんとなく不思議な異種交流(?)です。
というか、こんな写真撮ってしまって、これではまるで営業アライさんのよう...マズイ...
今日はK邸の、ここ1ヶ月の現場の様子をお伝えします

2007年12月21日(金)
上棟から一週間と半分をすぎた頃。
「北からの風で雪が中に吹き込んで、大変だったんだよ(ここの棟梁の
トクタケさん談)」ということで、ガラ(外壁下地板)を打つ前にとりあえず、
タイベック(外装下地用の透湿・防水シート)で壁を覆ってありました。
このときの内観は、
こんなかんじ。
施工される予定の樹脂サッシがすでに搬入されていました。
本仕事に取りかかる前に、明け方降り
積もった足場の雪をせっせと掃いてらっ
しゃいました。

2008年1月9日(水)
年末年始明けの9日に現場を訪ねると、ガラの施工がだいぶ終わっていました。
そして、玄関には注連縄が。
どうやら、休みに入ってからお施主さんが来て飾ってくださった様子。
新しく建てている家への想いが伝わってくるようで、うれしいかんじがします

この日トクタケさんは、屋根近くの壁のガラを打っていました。
ガラが打たれると、内観の印象もけっこう変わります。
すでにサッシがはめ込まれていました。
大工仕事は、いちおうの作業工程はあるものの、順序として「こうでなけ
ればならない」という決まりはなくて、現場の条件や大工さんのやりやすさ、
慣れなどによって進め方はまちまちです。
ただ、冬の間、現場は吹きっさらしで非常に寒いため、どの大工さんも
サッシはなるべく早めに入れるよう。
積まれていました。
2008年1月17日(木)
そしてこれが、今朝の様子。またしても雪景色です


トクタケ大工さんがいなかったので、中に入ることができず、せめてもと
庭のほうへ回ってみました

少しずつ家らしくなってきている感があります。
FLYING RAT(空飛ぶねずみ)とも称されるハトたちが、砂利の間にあるらしい何かをついばんでいます。
そしてそれを遠巻きにみつめるスズメたちの群れ...
というか、こんな写真撮ってしまって、これではまるで営業アライさんのよう...マズイ...
2008年01月16日
来週の上棟に向けての、刻み作業
会社の裏の作業場では、稲里のSさんの家の上棟に向けて、大工の
ヤマナカさんと、
キウチさんが準備を進めています。
何度となくご紹介しているように、当社は、データを入力して機械で材を
加工する"プレカット"ではなく、熟練の大工さんの手による"手刻み"で
ていねいに仕上げています

一本一本の木の性質、曲がりなどを確認しながら、墨を付け、刻んでいく
大工さんたちの姿を見ると、こうやって手をかける"家"というのはつくづく、
ただのモノや商品以上の存在だなあと感じたり。。
これもそれもみんな、Sさんの家を建てるために使われる材木です

写真の、積まれている材木はすべて刻み(構造材を組むための加工)が終わり、
所定の場所に立つのを待っている状態。
S邸の上棟は来週火曜日。大工さんたちの刻み作業も終盤です

2008年01月15日
床を張り終え、内部造作工事が進んでいます
1ヶ月以上ぶり、東口で工事が進むMさんの家

今日は大工さんが3人で作業をしていました。
この写真は、リビングになる予定の場所から、玄関の方向を見た様子。
年末年始のお休み前に設計士のセトさんが現場を訪れたときには、棟梁の
シオイリさんがリビングのフローリングを敷いているところでした↑
そして今日見てみると、すっかりきれいに養生されていて、一寸ほども
その様子をうかがうことができず...
あの赤みが強いカリン材のフローリングが、どのような姿を見せるのかは
養生がとれたときのお楽しみ、ということになります。。
LDKの天井下地であるプラスターボードも、このとおり、すでに施工済みです。
こちらのお宅では、Mさんの要望で幅3尺(90.9cm)の広縁が設けられています。
写真の屋根の勾配がうかがえる部分、ここが広縁に。
さて、和室になる予定のスペースでは、棟梁のシオイリさんが作業していました。
マスクをしているのは風邪をひいたから、ではなく、木を切断するときに出る
細かい木くずを極力吸わないようにするためのもの、なのだそう。
ちなみに今日は、今年御年99歳になるというシオイリさんのお母さんの
お話で盛り上がり(?)ました。
いまだお元気で、猫といっしょに散歩されているそうです。。
2Fでは、シゲオさんとオビナタくんがドア枠の施工作業などをしていました。
写真は、書斎になる予定の部屋から南面方向を望んだ風景。
そしてこの書斎、ピアノを置くということで、音対策がなされています。
すでに天井に施工されていたのが、防音天井材。
壁は、内側に遮音シートが張られる予定です。
2Fも大部分は天井が覆われてしまいましたが、和室になる予定の部屋だけ、
まだ小屋裏を見ることができます。
掲げられているのが見えました。
最終的にはすべての天井が覆われ、御幣棒は
家がなくなる日まで人の目にふれることなく家を
守りつづけます。
2008年01月11日
空調設備の施工と、大工さんの造作工事
モルタルの下地である黒色のラスが家のほぼ全面に張られ、着々と作業が
進んでいる感のある南高田Tさんの家

屋内はこのとおり。徐々に間取りが見えてきています。
壁面いっぱいに吹き付けられている淡いグリーンは、硬質ウレタン=断熱材。
T邸は高断熱・高気密住宅のため、十分な気密性と断熱性を確保するために
この断熱方法を採用しています。
さて、今日の現場では、空調・暖房屋さん(?)が換気設備や温水式
ファンヒーターのコンセントの取付作業をおこなっていました。
と同時に、大工さんたちが内部の造作工事に精を出していました。
若い大工のマーくんは、奥の洋室の窓枠を加工中。
ベテラン大工のコウメイさんは、差し金で寸法を測ったりしながら洗面
脱衣室のドア枠を施工中。
はしごを伝って2Fへ上がってみると、こちらは内部の造作がほとんどすべて
終わっていました。
大方の天井と壁は、すでにダンボール色のプラスターボードで覆われています。
ちなみにベランダは、ラスで覆われている状態。
なにげなく窓のほうに目をうつすと、見慣れない"つっかえ"が...
聞けばこれは、接着剤とビスで施工したばかりの窓枠がちゃんとおさまる
ようにするためのもので、数日間この状態で乾かすのだそうです。
2008年01月09日
お正月休み明けの現場の様子
11月末に上棟し、早くも1ヶ月以上を経た高田のUさんの家

外回りは、外壁下地とタイベック(外装下地用の透湿・防水シート)で覆われ、
サッシも玄関ドアもすべて施工済みです。
内観は、今はこんなかんじ。
ちょうど現場にいたとき、Uさんご夫婦と娘さんが3人で、大工さんに
お茶とお菓子の差し入れを届けにみえました。
中を興味深げに見渡していたUさんは、「間取りがわかるくらいになって
きましたねえ」と、感慨深げ。
はしごを登って、2Fへも足を踏み入れてみました。
今日は、雪かきで筋肉痛になったハラヤマさんが、一人で2Fの天井
下地を施工していました。
来週のウレタン(断熱材)吹付けに備えなくてはならないのだそう。
ちなみに普段いっしょに作業しているハラダ大工さんは、休暇の終盤
にきて風邪をひき、昨日も今日もお休みとのこと。。
ベランダもこのとおり、だいぶかたちになってきています。

2008年01月07日
新年あけましておめでとうございます
みなさま、新年あけましておめでとうございます

今日から2008年の営業がはじまりました。
まずは、社員みんなで工場の一隅に掲げられた神棚の前に集い、
安全・健康祈願。
本年も鎌倉材木店を、そしてブログ鎌倉日誌を、よろしくお願いいたします