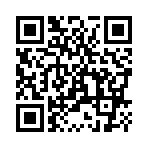2007年09月27日
県庁近くの平屋建て、上棟しました
さわやかな秋晴れの下、平屋建てを計画しているKさまの家の上棟が行なわれました。
上棟前日、土台を敷いたあとの現場の様子(養生シートに隠れてよく見えませんが...)。
そして、上棟。作業は着々と進んでいきます。
土台と柱の結合部は、"込み栓(こみせん)"という木製の棒で固定します。
これは、昔ながらの仕口の方法。
こちらのKさまの家には、薪ストーブが設置される予定。
リビングの太い梁と、火打ち梁(建物の水平方向へのねじれを防止する部材。
コーナーに施工する)は、表しで見せることになります。
ヤマモトさん。
後ろにそびえる朝日山、それに「柿」を取り込んで、秋らしさを演出してみました。
by営業アライさん
現場にあったクレーン車の運転席前のスペースに上らせてもらい、身体をよじり
ながら撮った渾身の一枚!なのだそうです。
秋を感じていただけますでしょうか?
上棟の現場には、施主のKさまも来て、写真を撮ってらっしゃいました。
日が暮れはじめたころ、棟上げが終わりました。
大きな片流れ屋根の平屋建て。
ガルバリウム鋼板と木をあしらった、モダンな印象の外観デザインになる予定です

棟上げを終えたら、お施主さま家族、工事関係者、みんな集まって上棟式です。
代理人のヨシダさん、大工のコウメイさんとヤマモトさんが、家の四隅に清めの
塩と米とお酒をまいて、工事の無事を祈ります。
「10年、20年経っても、鎌倉さんに頼んでよかった、と思えるような家を造って
ほしいです」とKさま。
そのご期待を胸に、これから内装・外装の工事が進められます

2007年09月21日
彼岸の入りに、地鎮祭
彼岸の入りの昨日20日。
長野市川合新田の一角で、Kさまの家の地鎮祭が執り行なわれました。
写真映えする青空です。
清めの切り幣を撒いたあと、
お施主さまが神さまに榊を捧げ、
土地の平安、工事の無事を祈る
玉串奉奠を行ないます。
まずは、K家のお父さんから。
その様子を見ていたご長男。
神主さんに、「ねえねえ、ぼくもやりたい」
お母さんに教わりながら、神さまに玉串を。
トミオカさんが、優しいまなざしで見守って
います。
心なしか、満足げなこの表情。
「これは一回で終わりなのよ」
「お兄ちゃん、だだこねちゃだめだよ」(弟くん)
などという会話がなされていたのかは、
定かではありませんが、
お子さんも参加して、地鎮祭は滞りなく
終了しました。
来年春の完成予定。
現場の代理人はマチダさんです。
2007年09月18日
"ベタ基礎"造り。
長野県庁の近くで工事がはじまったKさまの家。
若いご夫婦が住まうこの家は、こじんまりとしてシンプルな平屋建てに
なる予定です。
さて。
先週から今週にかけて、K邸の現場では基礎工事が行なわれていました。
木造住宅の建築で使う基礎には、いくつか種類がありますが
当社では、阪神淡路大震災以降、基礎の主流となりつつある
ベタ基礎を採用しています。
ベタ基礎とは、建物下の地盤を覆うように施工されたコンクリートの
面全体で家を支える、というもの。
地震や台風などの衝撃に強いとされている工法です。
そのベタ基礎造りの現場の様子↓
9月11日(火) 配筋工事

基礎屋さんの作業、まずはコンクリートを流し込む型枠作りと、鉄骨を組んで
いくことからはじまります。

ところどころにある円筒は、高さをそろえるための目印。
のちのち、抜き取ります。
9月12日(水) コンクリート流し込み

配筋工事の翌日。
いよいよコンクリートを流し込みます。
 「なんだ、ありゃ?」
「なんだ、ありゃ?」
写真を撮っていた営業アライさんが、
流し込まれたコンクリートの上にぽつんと
置かれた何かに気がつきました。

すると、基礎屋さんが長靴を履いたままおもむろにそれを両足に装着し...

まだゆるいコンクリートの上を、スタスタと歩きはじめました

「忍者が履くような水蜘蛛みたいな(アライ評)」この飛び道具(?)は、
"コンクリートかんじき"。
乾ききっていないコンクリート面を均す際、靴だとコンクリートの中に足が
埋まってしまうため、これを装着して作業するのだそう。。
現場には、見慣れない、興味深い道具がたくさんあります。
9月18日(火) 型枠外し

そしてそれから6日後の今日、型枠を外す作業が行なわれていました。
コンクリートはすっかり固まっています。
建築現場でよく見かけるであろうこの基礎は、こんなふうにして造られているのです。
若いご夫婦が住まうこの家は、こじんまりとしてシンプルな平屋建てに
なる予定です。
さて。
先週から今週にかけて、K邸の現場では基礎工事が行なわれていました。
木造住宅の建築で使う基礎には、いくつか種類がありますが
当社では、阪神淡路大震災以降、基礎の主流となりつつある
ベタ基礎を採用しています。
ベタ基礎とは、建物下の地盤を覆うように施工されたコンクリートの
面全体で家を支える、というもの。
地震や台風などの衝撃に強いとされている工法です。
そのベタ基礎造りの現場の様子↓
9月11日(火) 配筋工事
基礎屋さんの作業、まずはコンクリートを流し込む型枠作りと、鉄骨を組んで
いくことからはじまります。
ところどころにある円筒は、高さをそろえるための目印。
のちのち、抜き取ります。
9月12日(水) コンクリート流し込み
配筋工事の翌日。
いよいよコンクリートを流し込みます。
写真を撮っていた営業アライさんが、
流し込まれたコンクリートの上にぽつんと
置かれた何かに気がつきました。
すると、基礎屋さんが長靴を履いたままおもむろにそれを両足に装着し...
まだゆるいコンクリートの上を、スタスタと歩きはじめました

「忍者が履くような水蜘蛛みたいな(アライ評)」この飛び道具(?)は、
"コンクリートかんじき"。
乾ききっていないコンクリート面を均す際、靴だとコンクリートの中に足が
埋まってしまうため、これを装着して作業するのだそう。。
現場には、見慣れない、興味深い道具がたくさんあります。
9月18日(火) 型枠外し
そしてそれから6日後の今日、型枠を外す作業が行なわれていました。
コンクリートはすっかり固まっています。
建築現場でよく見かけるであろうこの基礎は、こんなふうにして造られているのです。
2007年09月12日
善光寺前の蕎麦処『藤木庵』さん、工事がはじまります。
善光寺参道の手前、善光寺郵便局の中央通りを挟んで向かい側に
お店を構える蕎麦屋『藤木庵』さん。
建て替えに際し、当社が施工を請け負うことになりました。
担当は当社の専務、代理人はクボさんです。
藤木庵さんのホームページを拝見したところ、こちらの創業は文政10年
(1827年)、江戸幕府第11代将軍家斉公の時代。
以来180年つづく老舗蕎麦処で、現在のご主人は7代目なのだそう。
今日足場が組まれ、いよいよ工事がはじまります。
この建物がどのように生まれ変わるのか、今からとても楽しみです

2007年09月10日
地盤調査と、風船唐綿
地盤調査とはなにか、ご存知でしょうか?
地盤調査、というのは、家を建てようとしている敷地が"軟弱地盤"で
ないかどうかを、専用の機械で確認する作業のことです。

この調査方法は"スウェーデン式サウンディング試験"と呼ばれます。
簡便なため、現在の日本の住宅の敷地調査ではよく用いられる方法です。
作業風景は、こんな雰囲気。
先にふれた軟弱地盤というのは、敷地の地層が泥土や腐食土で
構成されていたり、沼地や水田など水分の多い土地を埋め立てた
土地の地盤のこと。
つまり、不安定な地盤です。
敷地が軟弱地盤であることに気づかずに家を建ててしまうと、大きな
悲劇に見舞われる可能性が出てきます。
大きな悲劇、それは不同沈下。
不同沈下とは、 家の敷地の一部が不均一に沈みこんでしまう現象。
家がかたむき、最悪の場合住むことができなくなってしまう恐れがあるのです。
とくに長野市あたりは、土地の状態が一定ではありません。
たとえば、南長池のAさんのところは問題なかったのに、3軒先Bさんの
ところは軟弱地盤だった、ということもあります。
ただし、「軟弱地盤だから、家を建てるのはやめたほうがいい」
ということではありません。
地盤調査によって軟弱地盤だと事前にわかれば、地盤改良工事などを
することで、対策が十分可能です。
こと地盤に関しては、「知らないでいる」ことがいちばん怖いので、
敷地の地盤に対する不安を取り除くためにも、この調査はおろそかに
できないのです。

机の上に置かれたアライさんからのメモには「鬼灯(ほおずき)じゃないよ」の
一言が...
なんのこっちゃと写真を見ると、そこに写っていたのは微妙にとげとげした
みどり色のハリネズミのごとき植物...風船唐綿(フウセントウワタ)でした。
南アフリカ原産のこの植物、かなり繁殖力が高いそうです。
「鬼灯にしちゃ、でかいなあと思ったんだよ」って、アライさん...

花を入れた構図にこだわりつづけるアライさん。
いくらほかに花が見当たらないからって、キクというのはちょっと...
地盤調査、というのは、家を建てようとしている敷地が"軟弱地盤"で
ないかどうかを、専用の機械で確認する作業のことです。
この調査方法は"スウェーデン式サウンディング試験"と呼ばれます。
簡便なため、現在の日本の住宅の敷地調査ではよく用いられる方法です。
作業風景は、こんな雰囲気。
先にふれた軟弱地盤というのは、敷地の地層が泥土や腐食土で
構成されていたり、沼地や水田など水分の多い土地を埋め立てた
土地の地盤のこと。
つまり、不安定な地盤です。
敷地が軟弱地盤であることに気づかずに家を建ててしまうと、大きな
悲劇に見舞われる可能性が出てきます。
大きな悲劇、それは不同沈下。
不同沈下とは、 家の敷地の一部が不均一に沈みこんでしまう現象。
家がかたむき、最悪の場合住むことができなくなってしまう恐れがあるのです。
とくに長野市あたりは、土地の状態が一定ではありません。
たとえば、南長池のAさんのところは問題なかったのに、3軒先Bさんの
ところは軟弱地盤だった、ということもあります。
ただし、「軟弱地盤だから、家を建てるのはやめたほうがいい」
ということではありません。
地盤調査によって軟弱地盤だと事前にわかれば、地盤改良工事などを
することで、対策が十分可能です。
こと地盤に関しては、「知らないでいる」ことがいちばん怖いので、
敷地の地盤に対する不安を取り除くためにも、この調査はおろそかに
できないのです。
机の上に置かれたアライさんからのメモには「鬼灯(ほおずき)じゃないよ」の
一言が...
なんのこっちゃと写真を見ると、そこに写っていたのは微妙にとげとげした
みどり色のハリネズミのごとき植物...風船唐綿(フウセントウワタ)でした。
南アフリカ原産のこの植物、かなり繁殖力が高いそうです。
「鬼灯にしちゃ、でかいなあと思ったんだよ」って、アライさん...
花を入れた構図にこだわりつづけるアライさん。
いくらほかに花が見当たらないからって、キクというのはちょっと...
2007年09月05日
…忍者?
最近気になったできごとをひとつ。

先日アライさんが撮ってきた写真の中に、ぽつんと人が写りこんでいました。
「…忍者?」
黒子の青バージョンのような服に身を包んだ人が、組まれたばかりの
足場に座って、こっちを見ています。。
忍者にしては、ちょっとカップクがよろしいような...
あまりに不思議ないでたちのため、気になったので、写真を撮った
アライさんに聞くと、
「えー?人がいるのなんて気づかなかったよ」。
この日現場にいたマチダさんに確認すると、「…誰だこれ?こんな人見なかったよ」。
ん?
その場に居合わせた代理人のクボさんとヨシダさんに尋ねても、
「誰だこれー、見たことねえぞ」。
えー?!
誰も知らない業者の人?たまたま通りすがった通行人?それとも...??
忍者疑惑、いまだ未解決です。
先日アライさんが撮ってきた写真の中に、ぽつんと人が写りこんでいました。
「…忍者?」
黒子の青バージョンのような服に身を包んだ人が、組まれたばかりの
足場に座って、こっちを見ています。。
忍者にしては、ちょっとカップクがよろしいような...
あまりに不思議ないでたちのため、気になったので、写真を撮った
アライさんに聞くと、
「えー?人がいるのなんて気づかなかったよ」。
この日現場にいたマチダさんに確認すると、「…誰だこれ?こんな人見なかったよ」。
ん?
その場に居合わせた代理人のクボさんとヨシダさんに尋ねても、
「誰だこれー、見たことねえぞ」。
えー?!
誰も知らない業者の人?たまたま通りすがった通行人?それとも...??
忍者疑惑、いまだ未解決です。
2007年09月05日
「落日と案山子」、千曲市S邸の上棟(第二弾)
「今日のはコレがテーマだから」、と得意げな営業アライさん。
花シリーズを脱却して、新境地、案山子(かかし)を構図に取り入れて
みたようです。
しかしまたしても、ピンボケ写真(アライさん的には"ソフトフォーカス")...
その案山子が見守る先にあるのは、千曲市S邸の建築現場。
2棟同時に新築予定のS邸、昨日はその2つめの上棟でした。
写真奥に見えるのが、先に上棟しているSさまのご長男家族の家です。
この間大工のハラヤマさんに「大工さんで、高所恐怖症の人はいないのですか?」
と聞いたところ「いるさー、そういうやつは絶対上に登らないの」との答え。
つまり、この写真のような状況の場合、必ず下で支える役回りをしている
のですね。。。納得。
若手大工のコウジさんも、代理人のマチダさんも、がんばっています。
これは、2F部分の組み上げの様子。
陽が傾いてきました。
上棟も大詰め、大工さんたちが屋根の野地板を張っていきます。

タイトル「落日と案山子」byアライさん。
田んぼの案山子が見守る中、上棟が無事終了です。
日も暮れた頃、上棟式をとり行いました。
Sさまのお母さまは「1週間のうちに2棟も棟上げできるなど、めったにない
ことでしょうし、幸せなことです」と社長と話し、感激されているご様子でした

2007年09月03日
レモンイエロー色の花の正体
このあいだブログに「この写真の花が何の花かわからない」と書いたところ、
これから上棟を迎える施主のTさまが、お電話にて「あれはオクラの花
だと思うんだけど」と、教えてくださいました。
なるほどー

調べてみると、たしかにあの色あの形は、まさしくオクラの花のよう。
「畑に植わっていた」というアライさんの証言も納得できます。
身近なようで知らないことがたくさんあります...
勉強になりました。
Tさま、ありがとうございます

2007年09月03日
大工さんの道具<フィニッシュネイラー>
善光寺の近くで工事が進む2世帯住宅、Iさまの家の様子。
壁の下地材で空間が仕切られて、だいぶ住まいらしさが出てきています。
前に来たときにはなかった階段も設置されていました。
勾配は一般的らしいですが、ステップごとの幅がすこし広めにできているそう。
そのためか、上り下りがずいぶん楽にできるような感じがします。
2Fでは、大工のキウチさんが、トイレ空間を製作中。
造っています。
収納スペースの内装下地となるボードを
なにかでバチンバチンと留めていきます。
「それはいったい何ですか?」
「すごく細い釘を打ってるんだよ」。ヤマナカさんが教えてくれました。
このときヤマナカさんが使っていたすごく細い釘=フィニッシュネイルは、
長さ2.5cm、太さたったの0.6mmという極細の釘。
これを、フィニッシュネイラーという拳銃のような(あまりよいたとえではない
かもですが...)道具に装填して、銃の引き金を引くような要領でボードなどに
打ちつけていきます。
フィニッシュネイラー。
釘の太さに応じて、道具を変える必要が
あるため、ヤマナカさんも何台も持っている
のだそう。
釘の頭の部分がほとんどないフィニッシュネイル。
「仕上げ用の釘」という名前だけあって、ぱっと見、釘のあとがまったく見えません。
シャーペンの先でつついた?ほどの大きさの
点が、かすかに見受けられます。
昔ながらの大工の技を踏襲する一方、
作業効率と精度をあげるため、さまざまな
新しい道具も導入されているのが、大工さん
の仕事場です。
外ではイシザカさんが、"ラス"を張っていました。
ラスというのは、網目状の金属で、モルタルを塗る際の下地になります。
これを施工することで、壁材のくっつきがよくなったり、壁にヒビが入り
にくくなったりします。
ラスにもいくつか種類があり、ここでは波ラス(網目が普通の平ラスより
波打っていて、外装材のくっつき力が高くなる)と、平ラスを兼用していました。