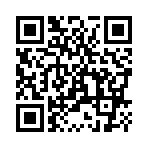2016年01月19日
Hさんのお住いが小布施町「優良な景観建築物等」の認定をいただきました!
昨年の話になりますが・・・

鎌倉材木店で施工させていただいたHさんのお住いが、小布施町
「優良な景観建築物等」の認定をいただきました!


この認定制度は、平成19年から始まり今回で8回目を迎えるそうです。
美しい街並みづくりにご協力いただいている建築物等について、
「まちづくりデザイン委員会」で、現地調査をはじめとした審査が行われ、
建物の形状や色彩、植栽等を総合的に判断し、認定をするそうです。
(小布施町 町報、HPより)
小布施と言えば景観の美しさが多くの人々を引きつけるまちです。
そこでこのような認定をいただけるのは嬉しい限りです
美しいといえば

昨年ブラックチェリー1枚板のテーブルを納品させていただいた、
川中島のNさんのお住い。今回はテーブルに合わせた椅子を
お届け致しました。一つひとつ違う座面の布地の色が、カラフルで
素敵な椅子でした

鎌倉材木店で施工させていただいたHさんのお住いが、小布施町
「優良な景観建築物等」の認定をいただきました!



この認定制度は、平成19年から始まり今回で8回目を迎えるそうです。
美しい街並みづくりにご協力いただいている建築物等について、
「まちづくりデザイン委員会」で、現地調査をはじめとした審査が行われ、
建物の形状や色彩、植栽等を総合的に判断し、認定をするそうです。
(小布施町 町報、HPより)
小布施と言えば景観の美しさが多くの人々を引きつけるまちです。
そこでこのような認定をいただけるのは嬉しい限りです

美しいといえば

昨年ブラックチェリー1枚板のテーブルを納品させていただいた、
川中島のNさんのお住い。今回はテーブルに合わせた椅子を
お届け致しました。一つひとつ違う座面の布地の色が、カラフルで
素敵な椅子でした

2015年09月03日
小布施の家が和モダンにて掲載されております

新建新聞社さんより『和モダンVol.8 家族を育てる住まい』が
発刊となりました。
今回、鎌倉材木店で施工させていただいた、「小布施の家」が
掲載されております。(設計は萌建築設計工房さん。)
伝統的な和様式に現代の生活スタイルを融合させた
素敵な和モダンの住宅が多数掲載されております。

雑誌掲載用のインタビューの様子です。

テラスから見た中庭。
長い庇により生まれた影と、光降りそそぐ
中庭のコントラストがとてもキレイです


本誌にも掲載されている「ワニさん」のアップ!
この脱力感がカワイイ

お住いを建てるまでのH様ご夫妻のお話も伺える、
読み応えのある一冊です。 全国の書店で取り扱って
いるそうですので、ぜひ一度ご覧ください。
2014年12月25日
ホームページ施工例に【小布施の家】掲載しました!

小布施町で完成したHさんのお住まいを、鎌倉の家 施工例に掲載しました

ぜひご覧ください!
~今日の小ネタです~
長野市三輪のTさんのお住いは土台の工事中。
そこで、木材の継手と仕口の一部を、ご紹介します。(詳しくは→こちら)
腰掛鎌継ぎ(こしかけかまつぎ)

継手(つぎて)=木材を長さ方向に接合する方法。また、その接合した箇所。
大入れ蟻掛け(おおいれありかけ)

仕口(しくち)=2つの木材を、直角あるいは斜めに接合する手法。また、その部分。

鎌倉材木店では、この継手・仕口を全て、大工さんの手で「刻み」を入れています。
大工さんの経験と技がここに生きているのです

2014年12月11日
小布施の京町屋風お住いが完成しました
先週末、小布施町のHさんのお住いが完成し、お引渡しとなりました。
設計は、萌建築設計工房さんです


屋根は三州日本瓦、外壁はそとん壁に杉板下見板張りと、
京町屋風の佇まい。中庭の造園工事はこれからになります。

お住い側の玄関。写真右の壁は杉羽目板張りです。
写真左の階段の段板は、Hさんの奥様のご実家で所有されている
山から伐採した杉の木が使用されてます。
正面のすりガラスから入るやわらかな光が、お客様をお迎えします


居住棟につながる廊下は、木目が美しい唐松フローリング。
廊下の途中にある4畳半ほどの和室の襖は、アワガミファクトリーから
取り寄せた「阿波紙」という和紙を使用しています。


こちらはLDK。1Fから2Fと、2Fからリビングをみたところです。
リビングの床から80cm程高くなったスペースは、TVコーナーになるそう。
吹き抜けの広々としたリビングは、開放感あふれる空間になっています。

リビングからみたキッチンサイドです。

家具屋さん手づくり、世界にひとつしかない造作キッチン
ステンレス水盤、ガスコンロ、食器洗浄機など、お好きなメーカーの
器具を組み合わせることが可能です。
壁側の収納、写真奥に見えるカウンターと壁掛棚もオリジナル造作家具です。

こちらも世界にひとつしかない造作洗面台


2Fキャットウォークから多目的コーナーを見たところです。
造作カウンターと棚が、ここにも設けられています。

こちらが施術所側の玄関になります。

施術所は床・壁ともに杉材を使用。扉を開けた瞬間に、木の良い香りがしました
洗面台と壁付棚もオリジナル造作です。

2Fの個室。普通、下地材として使用される合板を
あえて現(あらわ)しに。
木が持つ自然なあたたかさと、一つひとつの素材・ライティングなど、
細部にまでこだわったステキなお住いとなりました
設計は、萌建築設計工房さんです



屋根は三州日本瓦、外壁はそとん壁に杉板下見板張りと、
京町屋風の佇まい。中庭の造園工事はこれからになります。

お住い側の玄関。写真右の壁は杉羽目板張りです。
写真左の階段の段板は、Hさんの奥様のご実家で所有されている
山から伐採した杉の木が使用されてます。
正面のすりガラスから入るやわらかな光が、お客様をお迎えします



居住棟につながる廊下は、木目が美しい唐松フローリング。
廊下の途中にある4畳半ほどの和室の襖は、アワガミファクトリーから
取り寄せた「阿波紙」という和紙を使用しています。


こちらはLDK。1Fから2Fと、2Fからリビングをみたところです。
リビングの床から80cm程高くなったスペースは、TVコーナーになるそう。
吹き抜けの広々としたリビングは、開放感あふれる空間になっています。

リビングからみたキッチンサイドです。

家具屋さん手づくり、世界にひとつしかない造作キッチン

ステンレス水盤、ガスコンロ、食器洗浄機など、お好きなメーカーの
器具を組み合わせることが可能です。
壁側の収納、写真奥に見えるカウンターと壁掛棚もオリジナル造作家具です。

こちらも世界にひとつしかない造作洗面台



2Fキャットウォークから多目的コーナーを見たところです。
造作カウンターと棚が、ここにも設けられています。

こちらが施術所側の玄関になります。

施術所は床・壁ともに杉材を使用。扉を開けた瞬間に、木の良い香りがしました

洗面台と壁付棚もオリジナル造作です。

2Fの個室。普通、下地材として使用される合板を
あえて現(あらわ)しに。
木が持つ自然なあたたかさと、一つひとつの素材・ライティングなど、
細部にまでこだわったステキなお住いとなりました

2014年10月20日
小布施のHさんのお住い~パテ処理~
小布施町のHさんのお住まい、前回は外観の様子をお伝えしました。
今回は内部の様子です

と言いつつ、駐車場・下屋・通り土間のコンクリート工事の写真から始まります。
ここはカラーコンクリートを使用する予定。どんな色に仕上がるのか、楽しみです

仕事部屋の入り口は、吊り片引戸になっています。

こちらは仕事部屋の診療室になります。
床・壁ともに杉材を使用。木目が美しく落ち着いた雰囲気です。

仕事部屋2階の個室の天井は、登り梁(のぼりばり)です。
存在感のある梁は、以前お住いの家の梁を再利用したもの。
杉野地板と軒桁の間に、垂木の高さに合わせた二重窓が
納まっています。
やわらかい日射しが差し込む、明るい部屋になりそうです
※登り梁=梁が水平でなく屋根勾配などに合わせ、
斜めに架けられること。


こちらはお住い側。造作も終わり、パテ処理が始まりました。
仕事部屋2階と同じく、天井は登り梁(のぼりばり)になっています。

ロフト付きの個室です。
パテ処理後の仕上げは、合成樹脂エマルションペイント(EP)塗装に
なります。
EPは水を使った水系塗料で、健康や環境への影響が比較的少ない
塗料なのだそうです。

1階造作家具の下側で、パテ処理中のTさんは仕事をはじめて1ヶ月少し。
まだ10代の新人さんです
「顔がうつるのはちょっと・・」と言うことなので、後ろ姿を撮影
これから経験を積んで一人前の職人さんになっていくのですね
Hさんのお住い、完成までラストスパートです
今回は内部の様子です


と言いつつ、駐車場・下屋・通り土間のコンクリート工事の写真から始まります。
ここはカラーコンクリートを使用する予定。どんな色に仕上がるのか、楽しみです


仕事部屋の入り口は、吊り片引戸になっています。

こちらは仕事部屋の診療室になります。
床・壁ともに杉材を使用。木目が美しく落ち着いた雰囲気です。

仕事部屋2階の個室の天井は、登り梁(のぼりばり)です。
存在感のある梁は、以前お住いの家の梁を再利用したもの。
杉野地板と軒桁の間に、垂木の高さに合わせた二重窓が
納まっています。
やわらかい日射しが差し込む、明るい部屋になりそうです

※登り梁=梁が水平でなく屋根勾配などに合わせ、
斜めに架けられること。


こちらはお住い側。造作も終わり、パテ処理が始まりました。
仕事部屋2階と同じく、天井は登り梁(のぼりばり)になっています。

ロフト付きの個室です。
パテ処理後の仕上げは、合成樹脂エマルションペイント(EP)塗装に
なります。
EPは水を使った水系塗料で、健康や環境への影響が比較的少ない
塗料なのだそうです。

1階造作家具の下側で、パテ処理中のTさんは仕事をはじめて1ヶ月少し。
まだ10代の新人さんです

「顔がうつるのはちょっと・・」と言うことなので、後ろ姿を撮影

これから経験を積んで一人前の職人さんになっていくのですね

Hさんのお住い、完成までラストスパートです

2014年10月02日
京町屋風お住いのそとん壁
小布施町のHさんのお住まい、外壁の左官・塗装工事の様子をお伝えします

まずはモルタル下塗りからはじめます。
下地材はセーレン株式会社さんの「モルタルラミテクト」。
透湿性が高く、結露を抑え、モルタルの直塗りが可能だとか。
シートの上にメタルラスをタッカーで止めています。

下塗りが進んでいます

上塗りは、高千穂シラスさんの「スーパー白洲そとん壁W」。
「防水」と「透湿」の両方の機能を併せ持つ、100%自然素材の外壁材なのだそうです。

外壁の塗装が完成しました 一部ご紹介いたします。
一部ご紹介いたします。
こちらは仕事場です。

お住い側から、通り土間を見たところ。

ここは自転車などを置くスペースになるそう。

居住スペースに通じる玄関は、横格子の引き違い戸になっています。
外壁の塗装を終え、お住いの全体像が見えてくるこの時期は
撮影の度にワクワクします
Hさんのお住い、次回は内部の様子をお伝えしたいと思います。


まずはモルタル下塗りからはじめます。
下地材はセーレン株式会社さんの「モルタルラミテクト」。
透湿性が高く、結露を抑え、モルタルの直塗りが可能だとか。
シートの上にメタルラスをタッカーで止めています。

下塗りが進んでいます


上塗りは、高千穂シラスさんの「スーパー白洲そとん壁W」。
「防水」と「透湿」の両方の機能を併せ持つ、100%自然素材の外壁材なのだそうです。

外壁の塗装が完成しました
 一部ご紹介いたします。
一部ご紹介いたします。こちらは仕事場です。

お住い側から、通り土間を見たところ。

ここは自転車などを置くスペースになるそう。

居住スペースに通じる玄関は、横格子の引き違い戸になっています。
外壁の塗装を終え、お住いの全体像が見えてくるこの時期は
撮影の度にワクワクします

Hさんのお住い、次回は内部の様子をお伝えしたいと思います。
2014年07月30日
小布施町の造作現場にて (京町屋風のお住まい)
5月

小布施町のHさんのお住まいから 5~7月の造作工事の様子です。
5~7月の造作工事の様子です。
Hさんのお住まいは、京の町屋をイメージした造りになっています。

美しくそろった垂木(たるき)が、印象的な軒下
このように意匠的に見せる垂木をことを
「化粧垂木(けしょうたるき)」と呼ぶそうです。

ガラ(外壁の下地板)もきれいに張られています

美しいといえば・・
いつも通り整頓された道具置き場
物が無くなる!なんてことは、絶対起きなさそうです
6月


リビングのポイントとなる「化粧柱」
丸柱と床板が、隙間なくきれいに納まっています。

小布施といえば・・
『栗』 栗の花の時期は5~7月です。
栗の花の時期は5~7月です。
ちなみに栗の花言葉は「豊かな喜び・公平」なのだそうです。(諸説有)
7月

再登場の軒下です
「化粧垂木(けしょうたるき)」を支える横木は「軒桁(のきげた)」と言います。
唐松の1本ものです

こちら「下見板(したみいた)」張りの外壁。
Hさんのお住まいの下見板は「押縁(おさえぶち)」で押さえて止める方法です。
※下見板=外壁に張る横張りの板のこと ※押縁=板などを押さえる細い木のこと

土曜日は最高気温37°と、「超」猛暑でした
梅雨もあけ、本格的な夏の日差しの中で、
Hさんのお住まいの造作はこれからも続きます。
皆様も水分補給は、こまめになさってくださいね

小布施町のHさんのお住まいから
 5~7月の造作工事の様子です。
5~7月の造作工事の様子です。Hさんのお住まいは、京の町屋をイメージした造りになっています。

美しくそろった垂木(たるき)が、印象的な軒下

このように意匠的に見せる垂木をことを
「化粧垂木(けしょうたるき)」と呼ぶそうです。

ガラ(外壁の下地板)もきれいに張られています


美しいといえば・・
いつも通り整頓された道具置き場

物が無くなる!なんてことは、絶対起きなさそうです

6月


リビングのポイントとなる「化粧柱」
丸柱と床板が、隙間なくきれいに納まっています。

小布施といえば・・
『栗』
 栗の花の時期は5~7月です。
栗の花の時期は5~7月です。ちなみに栗の花言葉は「豊かな喜び・公平」なのだそうです。(諸説有)
7月

再登場の軒下です
「化粧垂木(けしょうたるき)」を支える横木は「軒桁(のきげた)」と言います。
唐松の1本ものです


こちら「下見板(したみいた)」張りの外壁。
Hさんのお住まいの下見板は「押縁(おさえぶち)」で押さえて止める方法です。
※下見板=外壁に張る横張りの板のこと ※押縁=板などを押さえる細い木のこと

土曜日は最高気温37°と、「超」猛暑でした

梅雨もあけ、本格的な夏の日差しの中で、
Hさんのお住まいの造作はこれからも続きます。
皆様も水分補給は、こまめになさってくださいね

2014年05月05日
小布施町で造作中!

小布施のHさんのお住まいの現場に行ってきました。

日本瓦の屋根が美しいです

Hさんのお住まいは、京の町屋をイメージした造りになっています。

こちらが仕事場になります。

仕事場の2階です。
以前お住まいになっていた、家の梁が見られます。

お住まい側から見た仕事場です。
住居棟と仕事棟の間に、坪庭〈つぼにわ〉のためのスペースが。
※坪庭=元々は町屋造りにおける主屋と離れとの間にある庭のことを言いました。

パントリーからダイニングキッチンを見たところです。
前回ブログよりも造作が進んでいます



事務机の上、パソコンのデスクトップなど、
仕事スペースには、それを使う方の個性がでますね

お住まい側の造作担当の大工Mさん。
作業しやすいよう、大工道具が一列にキチンと並んでいました。
あまりに
 キレイ
キレイ なのでアップしてしまいました。
なのでアップしてしまいました。2014年03月27日
小布施町で上棟しました!

3月24・25日の二日間、小布施町で上棟工事が行われました。
Hさんのお住まいと診療所の設計は萌建築設計工房さんです

奥の瓦屋根のお宅は、すでに上棟を終えた住宅です。
今回は、住宅手前の診療所の上棟となります。

3月24日(月)朝7時半過ぎ

すでに工事は始まっていました。

お昼過ぎには1階部分が完成し、2階部分に取り掛かっていました。
天気もよく、青空が広がる中での作業となりました

3月25日(火)
この日も天候に恵まれた暖かな一日となりました

東京では一部、桜の花も開花したとか・・
工事は夕方5時過ぎには無事に終わりました。


いよいよ上棟式が始まりました

上棟式とは、家を建てるときに、柱や梁(はり)など骨組みができて
棟木(むなぎ)を上げるときに行われます。
四隅にお酒、お米、塩をまいてお清めをします。

棟上げまで終了したことに感謝し、引き続き工事の安全を祈る
上棟式も無事に終わりました。
これからも大工さんの造作工事は続きます

※追記
上棟までをタイムラインで追ってみました。
上から順に24日(月)朝 → 昼 → 25日(火)夕 です。



徐々に骨組みが出来上がっていく様子が、少しでも伝われば嬉しいです

2014年03月13日
小布施町で造作中です

この日は肌寒かった先日とはうってかわって、ぽかぽか陽気となりました

小布施のHさんのお住まいは、2月の大雪も無事にのり越え、
順調に造作工事が進んでおります


瓦屋根にピョコっと煙突が!

実はこの辺りに、ダッチウェストのセコイヤという薪ストーブが入る予定です。
この薪ストーブはオーブン料理も楽しめるそうです


リビング側から見たダイニングキッチンスペース。
キッチン奥にはパントリーと呼ばれる食品収容スペースがあります。

今年2月10日のブログにもアップ
 しました
しましたリビングの柱です。
Hさんの奥様のご実家で所有されている山から
伐採した木が使用されてます。
傷がつかないよう、しっかり保護してあります


こちらは浴室になります。この写真だと、まだまだ完成後は想像しにくいのですが、
これからどのようになるのか楽しみです


1階からみた2階の様子。大工さんが作業をしているのが垣間見えます。
これからまだしばらく続く、造作作業。
次回は2階の様子もお伝えできればと思います

2014年02月10日
上棟がはじまりました
昨日、一昨日と大雪になりましたね
この休日は雪かきに追われた方も多いのではないでしょうか?
屋根の雪下ろしでの転落事故も増えていますし、雪下ろしの際はくれぐれもご注意ください。
さて、昨年11月に小布施町で地鎮祭をおこなったHさんのお住まいですが、
とうとう上棟作業へとうつりました
今日は上棟に至るまでの様子をご紹介
12月26日


設計士ワダさんに居間で使う柱を綺麗にしていると聞いて工場へ
高圧洗浄機を使って汚れを落としていきます。
2月3日

墨つけや刻みを終えた材木を現場に運び出していました。
7日から始まる上棟に向けて準備です
洗浄していた大きく太い柱も積まれています。
2月7日


上棟がはじまりました! タイミングを合わせながら木槌を叩いていきます。
今回Hさんのお住まいと大きな仕事場を同時に作るため、
作業が終わるまでに少し時間を要します
今週末には上棟式をおこなう予定です。
また上棟式の様子も随時お伝えしたいと思います

この休日は雪かきに追われた方も多いのではないでしょうか?
屋根の雪下ろしでの転落事故も増えていますし、雪下ろしの際はくれぐれもご注意ください。
さて、昨年11月に小布施町で地鎮祭をおこなったHさんのお住まいですが、
とうとう上棟作業へとうつりました

今日は上棟に至るまでの様子をご紹介

12月26日


設計士ワダさんに居間で使う柱を綺麗にしていると聞いて工場へ

高圧洗浄機を使って汚れを落としていきます。
2月3日

墨つけや刻みを終えた材木を現場に運び出していました。
7日から始まる上棟に向けて準備です

洗浄していた大きく太い柱も積まれています。
2月7日


上棟がはじまりました! タイミングを合わせながら木槌を叩いていきます。
今回Hさんのお住まいと大きな仕事場を同時に作るため、
作業が終わるまでに少し時間を要します

今週末には上棟式をおこなう予定です。
また上棟式の様子も随時お伝えしたいと思います

2013年11月12日
小布施町で解体工事・地鎮祭

10月21日から、小布施町のHさんのお住まいの解体工事が行われました

Hさんのお住まいは建替ということで、歴史を感じるお住まいを解体していきます。

曲がった木をうまく利用して造られた梁

この梁は大切にとっておき、新しい家でも梁として再利用します。
どのように生まれ変わるのか、今から楽しみです


解体工事が終わり、11月10日(日)に地鎮祭が執り行われました。
あいにく朝から雨が降っていて一日中降るのか心配でしたが、
地鎮祭を行う時には雨がおさまりました


地鎮祭が始まりました。神主さんが大幣で全員を祓い清めていきます。
大幣は祭場や神饌(お供え物)、参列者を祓い清めるための道具で、
榊の枝か白木の棒の先に紙垂(しで)をつけたもの。
この道具で祓い清めた後は、神様に工事の安全を祈り祝詞を奏上します


敷地の四隅と中央を祓い清め、災いが起きないように願います。
工事の無事・安全を祈り玉串を奉り、地鎮祭が終わりました

これから上棟に向けて準備開始です