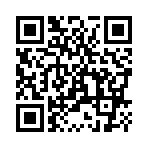2008年07月14日
一般住宅施工例に、北中のお住まいを掲載しました
4月にお引渡しした長野駅東口のMさんのお住まい。
お施主さまが楽しみにされていた夏椿が咲いたので、すっかりできあがった
外観の写真を撮影してきました。
エクステリアの工事や、庭木の移植もすっかり終了し、家が暮らしに
馴染みはじめていました。
外回りが整うと、より住まいらしくなります

壁はすべて塗り壁。
断熱材は、羊毛断熱材です

日立ハウステック社製のシステムキッチンは、桜色で華やかに。
見どころたくさんの、こちらのお住まいの様子を、
鎌倉材木店ホームページ 一般住宅施工例
にアップしました!
ぜひごらんください

2008年03月19日
風格ある和室と、サクラ色のシステムキッチン
長野駅東口で工事が進むMさんの家

こちらもお引渡しの日が近づいています。
3月2日(日) <代理人のウラノさん撮影>
3月はじめ、Mさんの家はまだ足場が組まれたままで、外壁の仕上げを待っている状態。
Mさんの家の内装は、すべて塗り壁。左官屋さんの腕の見せどころです

エコ建材"薩摩中霧島壁"が塗られます。
京壁塗りされる前の、和室の様子です。
3月19日(水)
そして、今日の日中の現場。
午前中に足場がばれたようで、外壁の仕上げを終えた外観の様子がよく見て
とれるようになっていました。屋根の上では、屋根屋さんが作業中。
上に写真で紹介した京壁塗り前の和室は、このように様変わり。
伝統的な和室の風格が漂っています。
畳も建具も入り、あとはコンセントの設置とクリーニングを待つのみです

LDKには、サクラ色のシステムキッチンとシステム収納が設置されていました。
とても華やかです。
LDK横のゲストルームも、明るくきれいに仕上がっています。
大きな鏡に、かわいらしい洗面ボウルが
見えます。
2F和室の壁には、丸い飾り棚。大工さんの手作りです

さらっと紹介しただけでも、見どころたくさんのこちらのM邸。
完成した姿を、どうぞお楽しみに☆
2008年02月14日
モルタル塗り
こちらも一ヶ月ぶり、長野駅東口で新築工事が進んでいるMさんの家

玄関ホールからして、ずいぶん様変わりしていました。
大工のシゲオさんは、玄関ドア上の壁のプラスターボードを加工し、張っている様子。
玄関すぐ横の8畳の和室は、まだちょっと雑然としています。。
LDKになる予定のスペース。
晴れた日の朝は、東に設置した窓から明るい陽の光が入り込みます

オビナタくんが、壁の下地を施工中。
食品庫の並びにあるゲストルームは、すでに壁にパテがかわれ、ひと足先に
大工仕事を終えています。
南に面した和室になるスペースでは、棟梁のシオイリさんが、タイガー印の
せっこうボード(ラスボード)を壁に入れていました。
つづいて2Fへ。
2Fはほぼ大工仕事が完了し、天井・壁にはパテがかわれて、左官屋さんの
仕事を待つのみとなっていました。
ここは、Mさんの書斎。造りつけの棚は、パソコンカウンターです。
大きなクローゼットがあるこの部屋は、寝室。
一方、2Fでこの部屋だけは、和室になります。天井はかわらず、むき出しのまま...
このようなかんじで、内部はずいぶんできあがりに近づいてきています

一方の外回りですが、今日は朝から石坂タイルさんがモルタルを塗っていました。
モルタルというのは、砂+セメント+水でできた建材で、家づくりでは外壁材として
多く使われます。
「よく混ぜる、っていうのが大切」とイシザカさんの奥さん。
でも混ぜ過ぎてなめらかになってしまうと、下地として都合が悪いそうで、そのいい頃合は「気候によってもちがうし、何度も失敗してつかんでいくものなのよねえ」とのこと。
工務店の家づくりというのは、つくづく、職人技の結集です。。
モルタルは、養生するのにある程度の日の光が必要で、さらに凍らせるととてもやっかい。
この時期は基本的に、晴れ間がでて、日中の気温がせめて1℃以上の日でないと作業ができないので、毎日天気予報とにらめっこしながら、仕事の段取りを決めているのだそうです。
週間天気予報をチェックすると、来週月曜日までは
 マーク。
マーク。藤木庵さんの左官工事もあるというし、なんとか晴れ間が出て、作業が予定どおり進むことを願います。。
2008年01月15日
床を張り終え、内部造作工事が進んでいます
1ヶ月以上ぶり、東口で工事が進むMさんの家

今日は大工さんが3人で作業をしていました。
この写真は、リビングになる予定の場所から、玄関の方向を見た様子。
年末年始のお休み前に設計士のセトさんが現場を訪れたときには、棟梁の
シオイリさんがリビングのフローリングを敷いているところでした↑
そして今日見てみると、すっかりきれいに養生されていて、一寸ほども
その様子をうかがうことができず...
あの赤みが強いカリン材のフローリングが、どのような姿を見せるのかは
養生がとれたときのお楽しみ、ということになります。。
LDKの天井下地であるプラスターボードも、このとおり、すでに施工済みです。
こちらのお宅では、Mさんの要望で幅3尺(90.9cm)の広縁が設けられています。
写真の屋根の勾配がうかがえる部分、ここが広縁に。
さて、和室になる予定のスペースでは、棟梁のシオイリさんが作業していました。
マスクをしているのは風邪をひいたから、ではなく、木を切断するときに出る
細かい木くずを極力吸わないようにするためのもの、なのだそう。
ちなみに今日は、今年御年99歳になるというシオイリさんのお母さんの
お話で盛り上がり(?)ました。
いまだお元気で、猫といっしょに散歩されているそうです。。
2Fでは、シゲオさんとオビナタくんがドア枠の施工作業などをしていました。
写真は、書斎になる予定の部屋から南面方向を望んだ風景。
そしてこの書斎、ピアノを置くということで、音対策がなされています。
すでに天井に施工されていたのが、防音天井材。
壁は、内側に遮音シートが張られる予定です。
2Fも大部分は天井が覆われてしまいましたが、和室になる予定の部屋だけ、
まだ小屋裏を見ることができます。
掲げられているのが見えました。
最終的にはすべての天井が覆われ、御幣棒は
家がなくなる日まで人の目にふれることなく家を
守りつづけます。
2007年12月06日
美しい小屋組と、羊の毛の断熱材ふたたび
昨日の夕方のこと。
「カナダって、空が真っ赤なんだよ」と、営業アライさん。
「つまりどういうこと?」とたずねると、
「カナダの空は、真っカナダ(赤だな)」
「・・・」 (風吹きすさぶ−30℃の雪原の真っ只中にいる心地)
年末のごあいさつまわり兼カレンダー配りに奔走していて、
"芸術作品"を撮影している余力もないとは聞いたけれど、
こんなダジャレを口走ってしまうほどにアライさんはお疲れのようです...
それはさておき。
ここ数ヶ月で上棟した家はそれぞれ、順調に建築工事が進んでいます。
今日は、東口で工事中のMさんの家の様子。

11月のはじめ、こんな風に屋根屋さんが瓦屋根を葺いていたMさんの家。

1ヶ月とすこし経った昨日の家の立ち姿がこちら。
周りはガラ(外壁下地)を張り終わり、サッシもすべて施工済です。

玄関ドアもすでに納まっています。
ここから中へお邪魔すると...


床にはコンパネが敷かれ、壁はところどころにすでに断熱材が入れられ、
すこしずつ家らしさを増している様子。

M邸の棟梁シオイリさんは、敷居を造っていました。
その場で長さを測り、材を切って調節し、

所定の位置にはめ込み、ビスで留めて据えつけます。
「やってみる?カンタンだし、楽しいよ~」とシオイリさん。
もちろん丁重におことわりです。

一緒に作業している大工のシゲオさんは、ユニットバス上の壁の下地を
造っていました。
差し金(L字型の定規)で角度を見ながら、微調整を繰り返します。
これもまた、細やかな仕事。

この間訪ねたときにはまだ未完成だった階段が、できあがっていました。
さっそく2階へ。

階段を登っていって、まず視界に入ったのがこの小屋組。
天井で隠れてしまうのがもったいないほど美しく、なんだか圧倒されてしまいました。。
「この家、すっごい美しい小屋組ですねえ 」
」
とシオイリさんにいうと、
「設計士さんの図面がいい図面なんじゃないかー?」
との答え。
いつも謙遜気味のシオイリさんですが、こういうのは設計士さんが描く
よい図面と、それをかたちにする大工さんの腕の両方があって、
はじめて実現できるものだよなあと、しみじみ。

2Fでは若い大工のオビナタくんが黙々と、天井の下地を施工中。

ふと見ると、2Fの一隅に白いふわふわした固まりが置かれていました。
見覚えのあるこれは、そう、羊の毛。
「使う建材は、可能なかぎり自然の素材で」というお施主さんの要望で、
断熱材は羊毛製品を使うことになりました。
現在、お引渡し間近の吉田のIさんの家と同じ。


2Fは大部分の壁に、すでに断熱材が施工してありました。
近寄って香ってみましたが、においはやっぱり無臭です。
お話に聞くかぎり、住まいの随所に個性やこだわりが見えるMさんの家。
今後の工事の進行が楽しみです。
「カナダって、空が真っ赤なんだよ」と、営業アライさん。
「つまりどういうこと?」とたずねると、
「カナダの空は、真っカナダ(赤だな)」
「・・・」 (風吹きすさぶ−30℃の雪原の真っ只中にいる心地)
年末のごあいさつまわり兼カレンダー配りに奔走していて、
"芸術作品"を撮影している余力もないとは聞いたけれど、
こんなダジャレを口走ってしまうほどにアライさんはお疲れのようです...
それはさておき。
ここ数ヶ月で上棟した家はそれぞれ、順調に建築工事が進んでいます。
今日は、東口で工事中のMさんの家の様子。
11月のはじめ、こんな風に屋根屋さんが瓦屋根を葺いていたMさんの家。
1ヶ月とすこし経った昨日の家の立ち姿がこちら。
周りはガラ(外壁下地)を張り終わり、サッシもすべて施工済です。
玄関ドアもすでに納まっています。
ここから中へお邪魔すると...
床にはコンパネが敷かれ、壁はところどころにすでに断熱材が入れられ、
すこしずつ家らしさを増している様子。
M邸の棟梁シオイリさんは、敷居を造っていました。
その場で長さを測り、材を切って調節し、
所定の位置にはめ込み、ビスで留めて据えつけます。
「やってみる?カンタンだし、楽しいよ~」とシオイリさん。
もちろん丁重におことわりです。
一緒に作業している大工のシゲオさんは、ユニットバス上の壁の下地を
造っていました。
差し金(L字型の定規)で角度を見ながら、微調整を繰り返します。
これもまた、細やかな仕事。
この間訪ねたときにはまだ未完成だった階段が、できあがっていました。
さっそく2階へ。
階段を登っていって、まず視界に入ったのがこの小屋組。
天井で隠れてしまうのがもったいないほど美しく、なんだか圧倒されてしまいました。。
「この家、すっごい美しい小屋組ですねえ
 」
」とシオイリさんにいうと、
「設計士さんの図面がいい図面なんじゃないかー?」
との答え。
いつも謙遜気味のシオイリさんですが、こういうのは設計士さんが描く
よい図面と、それをかたちにする大工さんの腕の両方があって、
はじめて実現できるものだよなあと、しみじみ。

2Fでは若い大工のオビナタくんが黙々と、天井の下地を施工中。
ふと見ると、2Fの一隅に白いふわふわした固まりが置かれていました。
見覚えのあるこれは、そう、羊の毛。
「使う建材は、可能なかぎり自然の素材で」というお施主さんの要望で、
断熱材は羊毛製品を使うことになりました。
現在、お引渡し間近の吉田のIさんの家と同じ。
2Fは大部分の壁に、すでに断熱材が施工してありました。
近寄って香ってみましたが、においはやっぱり無臭です。
お話に聞くかぎり、住まいの随所に個性やこだわりが見えるMさんの家。
今後の工事の進行が楽しみです。
2007年10月22日
善光寺木遣り響く、上棟式
先週金曜日に行われていた東口Mさまの家の上棟のつづき。

憂いていたとおり、昼頃から雨が本降りになってきてしまいました
しかしそれで作業が中断、ということにはもちろんなるはずもなく、
大工さんたちは雨具を着込んで作業を続けています。

雨にぬれた材木の上は滑りやすく、いつもにも増して気をつかいながらの
作業です。

雨は降っているし、日が落ちて暗くなってくるし、ということで、作業を
ふだんよりも早めの工程で切り上げて、上棟式です。
お酒とお米と塩を家の四方に撒き、お施主さま、大工さんたち、当社
スタッフみんなで工事の無事を祈願します。

上棟式の最後は、大工さんたちが輪になって、上棟祝いの気持ちを表す
「木遣り(きやり)」を唄います。
木遣り、というのはもともとは、大きな材木を人々が力を合わせて運ぶときの
掛け声として唄われていた労働歌。
長野市周辺で歌われる木遣りはとくに「善光寺木遣り」といわれ、もともとは
1666年と1707年の善光寺再建のときに、江戸から来た棟梁によってもたら
された唄が、口伝で今に伝えられているとされるのだそう(長野市教育委員会
の資料による)。
ここの現場のシオイリ棟梁の音頭で、大工さんみんなが唱和し、組上げられた
ばかりの家の下で響く木遣り唄。
最近では上棟式それ自体を省くケースも多いと聞きますが、鎌倉材木店の
家づくりでは未だところどころに、昔から受け継ぐ家づくりの精神を垣間見る
ことができるのです。

金曜日の天気が幻のように、土曜日も日曜日も今日も、すっきりきれいに
晴れました(社内では、代理人ウラノさん雨男説が囁かれています...)。
来年3月の完成にむけて、工事が進められていきます。
憂いていたとおり、昼頃から雨が本降りになってきてしまいました

しかしそれで作業が中断、ということにはもちろんなるはずもなく、
大工さんたちは雨具を着込んで作業を続けています。
雨にぬれた材木の上は滑りやすく、いつもにも増して気をつかいながらの
作業です。
雨は降っているし、日が落ちて暗くなってくるし、ということで、作業を
ふだんよりも早めの工程で切り上げて、上棟式です。
お酒とお米と塩を家の四方に撒き、お施主さま、大工さんたち、当社
スタッフみんなで工事の無事を祈願します。
上棟式の最後は、大工さんたちが輪になって、上棟祝いの気持ちを表す
「木遣り(きやり)」を唄います。
木遣り、というのはもともとは、大きな材木を人々が力を合わせて運ぶときの
掛け声として唄われていた労働歌。
長野市周辺で歌われる木遣りはとくに「善光寺木遣り」といわれ、もともとは
1666年と1707年の善光寺再建のときに、江戸から来た棟梁によってもたら
された唄が、口伝で今に伝えられているとされるのだそう(長野市教育委員会
の資料による)。
ここの現場のシオイリ棟梁の音頭で、大工さんみんなが唱和し、組上げられた
ばかりの家の下で響く木遣り唄。
最近では上棟式それ自体を省くケースも多いと聞きますが、鎌倉材木店の
家づくりでは未だところどころに、昔から受け継ぐ家づくりの精神を垣間見る
ことができるのです。
金曜日の天気が幻のように、土曜日も日曜日も今日も、すっきりきれいに
晴れました(社内では、代理人ウラノさん雨男説が囁かれています...)。
来年3月の完成にむけて、工事が進められていきます。
2007年10月19日
安全祈願で、上棟はじまり
今日は長野駅東口で新築するMさまの家の上棟の日。
朝8時。冷たい風が吹きすさぶ中、集まった大工さんたちが、前日に組まれて
積まれていた部材にかぶせたシートをきれいにたたみはじめました。
シートが取り払われて、すっきりしたら...
現場代理人のウラノさんが声をかけ、みんなで工事の安全祈願をして、
お神酒をいただきます。
だれですか、「(酒)足りねーなあ」なんて言っているのは...

安全祈願を終えたら、さっそく建て方作業のはじまり。
この現場の棟梁はこの方、シオイリさんです。
タケダさんが運転するクレーンで部材を吊り上げ、移動させて、
それぞれの納まり(接合部)を確認したら、マキオさんが掛け矢(木槌)で
継手部分を打ち込みます。
作業は手際よく、さくさくと進んでゆきます。
今日集まった大工さんたちは、みんなよく気心の知れた者同士のようで、
声を掛け合いながら、ときおり冗談いいながら、現場は和やかな雰囲気。
ふと見ると、キウチさんとマキオさんが、それぞれフレームの角に立っていました。
お二人とも立ち姿が格好いいです。でも、ほんとうに怖くないのだろうか...
40分ほどで、1F部分のフレームが組み上がりました。
熟練の大工さんの集団だけあって、作業に滞りがありません。
現在も東口の現場では作業が進められています。
午後もなんとか天気がもてばよいのですが...

2007年08月10日
東口M邸の地鎮祭(とこしずめのみまつり)
すきっと晴れ上がった9日の午前中、Mさま邸の地鎮祭がとり行われました。
神事を司るのは、戸隠宝光社の神主トミオカさんです。
敷地の四隅には、「四神」と呼ばれる天の四方をつかさどる神を見立てます。
東は青竜、西は白虎、南は朱雀で北は玄武。
それぞれ宿る神さまたちに細かく切った紙「切幣(きりぬさ)」をまき、清めます。
施主であるMさま、設計担当のセトさん...建築に関わるすべての人が
工事の安全と無事を祈ります。
設計室のワダさん、みんなで記念撮影。
まだまだ暑い日がつづきますが、お盆
明けにはこちらの現場も動きはじめます。