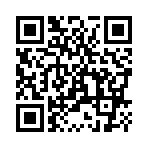2007年08月31日
建材モイス(Moiss)
長野市吉田で建設が進む、Iさまの家。
昨日もハラダさんとハラヤマさんが、大工仕事に精を出してらっしゃいました。
扇形国産ヒノキ大黒柱、羊毛断熱材、スギ材無垢フローリングなど、これまでも
お施主さまのこだわりが随所に散りばめられたこのI邸。
今回の注目はこちら、耐力面材(内装材)モイス(Moiss)です。厚さは12mm。
通常、内装は下地を張り、その上にクロスを張ったり漆喰を塗ったりして
仕上げますが、モイスはこのボード自体がむき出しの壁になります。
イメージが沸かない方、こちらをごらんください→施工例
一見、なんの変哲もないただの白いボードのようにも見えますが、じつは
さまざまな機能を秘めたエコ建材なのだそうです。
代理人のヨシダさんからもらった資料によると、その機能とは、
耐震性(地震に強い)
耐火性(火に強い)
耐久性(腐食・シロアリに強い)
調湿効果
脱臭効果
天然素材で環境配慮
施工性(これは大工さんにとっての利点ですが...)
このような利点の一方で、カラーバリエーションが少なく、さわった
かんじザラザラしていて、さらに施工面積あたりのコストが割高になる、
という側面もあります。
I邸では、お施主さまのご希望で、収納スペースにのみ、モイスを
採用することになっています。
一部施工された部分が、こちら↓
...アライさん、これ何ですか?
「写真、ありゃソフトフォーカスになっちゃってるね」、じゃありません。
これはたんなるピンボケです。。
写真を撮ってきてくれた営業のアライさん、どうやら撮影に際して
スペースの関係上十分に後ろへ引くことができず、全景写真のはずが
こんな至近距離しか撮れなかったのだそうです...

加工しておきます。
"木材のような加工性"をうたうモイスだけ
あって、きれいに切り取られています。
アライ流"ソフトフォーカス"のため、断面が
ぼんやりとしている点は、ご容赦ください。。
2007年08月29日
割烹さがみさま、リニューアルオープンです。
本日リニューアルオープンを迎える長野市権堂の「割烹さがみ」さま。
無事に工事が終わり、現場責任者のイワクラ常務もウラノさんも
ホッとひと安心の様子です。
**********************************
「割烹さがみ」 ホームページはこちら
http://park14.wakwak.com/~endou/
**********************************
外観はこちら。
ライティングによって闇に浮かび上がるシルエットが、建物の存在感を増しています。
黒色の外壁が斬新。
趣向がこらされた玄関前の空間。
玄関に入り、坪庭を横目にみながら風除室を過ぎた先にあるのが
この玄関ホール。(照明の関係で、写真がちょっと黄味がかっていますが...)
そしてホールに入って左手に広がるのが、こちらのカウンター席。
格式ばった意匠や、豪華な装飾のない数寄屋造り風建築の新生「割烹さがみ」。
軽やかにして細やかな意匠が見て取れます。あ、板さんが。
"数寄屋造り"というのは、日本の伝統建築様式のひとつ。
「数寄」(数奇)とは、和歌や茶の湯、生け花など風流を好むことを表し、
「数寄屋」は、「好みに任せて作った家」とされ、茶室を意味します。
1Fの大人数用お食事スペース。
このようにひとつづきの大広間にもなるし、襖で仕切って個室としても
使うことができます。
ちなみに、手前に座ってらっしゃるのは、さがみのオーナーの遠藤氏。
その奥に座ってらっしゃるのが、この建築の意匠設計をされた鈴木氏。
こちらのお部屋は、窓からお庭を望むことができます。
照明のデザインや欄間の意匠にも、個性が光ります。
さて、こちらは2F廊下です。
天井にほどこされた小さなお花の意匠に、遊び心が見えます。
シンプルで洗練された印象の空間。
2Fにあるこの宴会場は、もともとの建物をリフォームしました。
奥の個室へとつづく廊下。
天井から下がる"下地窓"は、数寄屋造りに特徴的な意匠。
"下地窓"は、土壁を塗り残したままで、下地が見えている窓のこと
(ここでは厳密には窓ではなく、純粋に装飾ですが)。
茶道を大成したといわれる千利休が、田舎家の実例を見て風炉先窓に
とり入れたのがはじまり、といわれるのだそうです。
上写真の廊下を突きあたって左の奥にある女性用化粧室。
下地窓ややわらかな曲線の柱など、茶室の水屋を模した空間です。
昨夜、写真撮影に行くとSBCのテレビクルーが、さがみさんのCM撮影を
していました。
板さんたちが勢ぞろいです。
「割烹さがみ」でお食事の際は、お料理とともに、当社が手がけた建築も
堪能していただければ幸いです

2007年08月28日
千曲市S邸、上棟(第一弾)
すこし前のことになりますが、8月23日(木)千曲市で建設工事が
始まっていたSさまの家の上棟が行なわれました。
ひとつの敷地に2棟の家が建つ予定のSさま邸。
今回はまず1棟目の上棟です。
あいかわらず、花を構図に入れることに余念がない営業アライさん。
このレモンイエロー色の花は...調べたもののわかりませんでした

花の雰囲気は、フヨウやムクゲに似ていますが、葉っぱのかたちが異なるよう。
「畑に植わっていたよ」とアライさん。食用のなにかなのでしょうか?
構造材を組み上げていきます。
こんな高い位置にある幅の狭い材の上に
バランスよく立っていられるということは、
戸隠山の蟻の塔渡りだってへっちゃらなの
ではないかと思われます。
ハワイに行ってきたかと見紛うほどに
こんがり美しく日焼けしていますが、
残念ながらただの現場焼けです

それにしてもこの写真、アングルが妙に
隠し撮りっぽいですよ、アライさん...
ところで、こちらのS邸の敷地は、高さが隣を走る道路よりもすこし
低かったため、土を盛って造成してあります。
のちのち回りに土留めを造って、地面の崩れを防ぎます。
花を入れた構図の写真は、まだあります。
上棟風景が、ちょっと遠いような...
この写真にいたっては、あざやかなマツバボタンに集中したあまり、
メインのはずの上棟風景がフレーム外に切れています。。
日がだいぶ傾きかけたころ、無事にS邸が上棟しました

お施主さま家族といっしょに、上棟式です。
大工のアライさん、コウジさん、代理人のマチダさんがそれぞれ清めの
塩・酒・米を手に、工事の無事を祈ります。
「今まで転勤が多く、官舎での生活が長かっただけに、今回はじめて
我が家をもつことができ、感無量です」とSさん。
家の立ち姿を目にするとにわかに家を持つという実感がわいてきて、
お施主さまにとっては喜びもひとしおのよう。
S邸の上棟第2弾も、まもなくです。
2007年08月23日
割烹さがみさま、完成間近です。

権堂で工事が進められている「割烹さがみ」さま。
当社で製材し、大工のシオイリさんが磨き上げた一枚板は、このような
立派なカウンターになりました。
今月29日のリニューアルオープンを前に、外溝を請け負う造園屋さん、
お店の従業員の方々、大工さんがそれぞれ準備に追われています。
中の様子をすこし。これは、2Fの一隅。
天井や手洗い場をはじめ、選び抜かれた
照明とこまやかなディテールが目を引きます。
下のふたつの写真のような細工は、指物師
さんの仕事。
店内は、間接照明の配し方も巧みです。
ディテールへのこだわりは、照明だけではありません。
このような障子窓の波形格子や、市松模様的な畳など、粋な遊び心が随所に
見られます。
オープンまであと7日。完成が楽しみです。
2007年08月22日
南高田T邸の地鎮祭(とこしずめのみまつり)
強い日差しが照りつけるこの日曜日の午前中、南高田でTさまの家の
地鎮祭がとり行われました。
ひきつづき、「花」を写真の構図にとりこむことにこだわる営業アライさん。
「今回は"ニラ"の花だから」。...ニラ?草?
神主のトミオカさんが四方位の神々に祝詞をあげ、工事の無事と家の安全を祈ります。
ご家族の皆さまがひとりひとり、神主さんから榊を受け取り、神さまに捧げます。
この日は、近くに暮らすTさまの奥様のご両親も参加されました。
Tさま家族の家は2世帯住宅で、来春の完成を予定しています。
2007年08月18日
スギ無垢フローリングを敷いています
ヒツジの毛の断熱材(羊毛断熱材)を使うなど、素材にこだわった家づくりを
すすめている長野市のIさま。
フローリング材も、「スリッパを履く必要がなく、素足で歩いて気持ちがいい
床にしたい!」というご家族たってのご希望で、スギの無垢フローリングを
使うことになりました。
大工のハラヤマさんが、ていねいに施工中です。
通常、当社としては無垢フローリングにはナラ材をお奨めしています。
ナラは硬い材質の木で、キズがつきにくく、耐久性が高いからです。
でもIさまご家族は熱心に情報収集され、結果として軟らかい性質で
ナラに比べるとキズがつきやすいスギを選ばれました。
「人が住んでいればキズはつくもので、それもまた味わい。それよりも
心地よさを大事にしたい」というIさま。
家づくりを考えていると、とかく、機能性や利便性を優先させてしまい
がちですが、時にはIさま家族のように心地よさや気持ちよさといった
肌感覚も大切にしたいものです。
壁には、ヒツジの毛の断熱材が、ぎっしり充填されていました。
ほわほわしていて、暖かそう(暑そう?)です。
2007年08月17日
2世帯住宅、ナラ無垢フローリング施工の様子
先日ご紹介した"連棟分離タイプ2世帯住宅"の篠ノ井のTさまの家に対し、
こちら、善光寺近くで建設中のIさまの家は、"上下分離タイプ2世帯住宅"です。
I邸の場合、下が親御さん夫婦、上が若夫婦家族の居住空間。
この日は、大工さんたちがフローリング材を張っていました。
I邸ではリビングや寝室など主だった部屋の床材は、ナラの無垢フローリング。
ナラは、木質が硬く、耐久性が高いのが特徴です。
床の断面、クッキーの間に挟まっているクリームのように(?)厚く白っぽい
部分は、ユカテックという遮音のための建材。
上下分離タイプの2世帯住宅では、階下への生活音がしばしば問題になるため、
その対策として遮音性に優れた建材を施工するのです。
2007年08月10日
東口M邸の地鎮祭(とこしずめのみまつり)
すきっと晴れ上がった9日の午前中、Mさま邸の地鎮祭がとり行われました。
神事を司るのは、戸隠宝光社の神主トミオカさんです。
敷地の四隅には、「四神」と呼ばれる天の四方をつかさどる神を見立てます。
東は青竜、西は白虎、南は朱雀で北は玄武。
それぞれ宿る神さまたちに細かく切った紙「切幣(きりぬさ)」をまき、清めます。
施主であるMさま、設計担当のセトさん...建築に関わるすべての人が
工事の安全と無事を祈ります。
設計室のワダさん、みんなで記念撮影。
まだまだ暑い日がつづきますが、お盆
明けにはこちらの現場も動きはじめます。
2007年08月09日
篠ノ井2世帯住宅の途中経過
篠ノ井で工事が進むTさま邸は、"連棟分離タイプ"の2世帯住宅です。
「ひとつの家に世代のちがう2家族が一緒に暮らす」、という性質上、
2世帯住宅の家の造りには、いくつかのパターンがあります。
この場合の連棟分離タイプとは、
"玄関はひとつ、家は2棟別々、双方を廊下でつなぐ"形式の造り。
手前、和風な趣きの平屋造りが親御さんの住まい、奥に見える2階建てが
若夫婦家族の住まいです。
両方の家の間に配された、家族共有の玄関。
梁や垂木を表わしにした、純和風の意匠が特徴的です。
玄関に入って、向かって左が親御さんの住まい。
まだ基礎がみえているこの状態では、まだちょっとわかりにくいですが。
こちらは、平屋から、玄関・若夫婦の家方向をのぞんだときの風景。
廊下が一直線に、若夫婦の家へ向かって続いているのがわかります。
ちなみに写真右寄り正面に見える際立って太い柱は、6.5寸角のヒノキ材。
小窓を設置。
プラン上、暗くなってしまう居室間の廊下の
明かりとりです。
小屋裏では、大きな太鼓梁が屋根を支えています。
すでに階段が設置されています。
平屋と同じく、2F小屋裏もまだむきだしの状態。
この家では、強度の高い太鼓梁が3本使われているのがわかります。
家づくりをご検討中で、この住宅の構造等をご覧になりたい方は、
ぜひ電話かメールでお問い合わせください。
建築現場へご案内いたします。
tel. 026-221-5375
E-mail. info@kama-kura.com
2007年08月06日
ヒツジの毛の断熱材、カメ模様の砥石台
こちら、長野市吉田で工事がすすめられているI さま邸です。
今日の昼間の様子。
夕方の黒い空と、激しい雷雨が嘘のような晴れっぷりです。
Iさん家族は、時間をかけて住まいを検討されました。
自然の素材をたくさん使った、健康で心地よい家を、ということで
家づくりの材料にもこだわりが見えます。
そのひとつがこの断熱材。
ヒツジの毛を使った"羊毛断熱材"です。
今回使うのはサーモウール<エクセレント>。
羊毛85%、中空ポリエステル系繊維15%
で、湿度の高い環境や季節の温度差が
大きい地域、シックハウス対策に高い
性能を発揮する、のだそう。
断熱・調湿性能が高く、同時に生産や
廃棄の点で環境負荷が低いことが評価
されている断熱材です。
この写真を目にした設計室のマチダさんが「何それ、腸?」などと
言っていますが、ちがいます、断熱材です。
ほかほかした手ざわりで、羊毛布団を彷彿とさせます。
においは...嗅いでみたところ、ほぼ無臭でした。
ほのかに、ヒツジのよい香りがした気が...
残念ながら、今日は大工さんたちがほかの現場の建舞でいなかった
ため、作業中の様子は撮れませんでした。
2Fの壁が、一部施工済みだったので、その写真です。
このような感じで、I邸はヒツジの毛にくるまれてゆきます。
代理人のヨシダさんと設備屋さんが
現場で打合せをしていました。
代理人さんは、こんな風に各専門の業者
さんたちと話を重ねながら、ひとつひとつ
工程を進めていくのです。
ありました。
このカメ模様の砥石台です。
砥石は、ノミやカンナを研ぐための必需品。
2つあった砥石台のうち、ひとつは無地の
シンプルな台だったのですが、もうひとつは
このカメ&波模様でした。
こんなふうに、大工さんの使う道具には、
鶴や亀など、縁起物をあしらった意匠が多く
見られます。