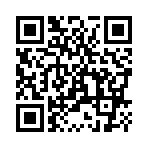2014年09月30日
長野市上野で上棟しました!
9月26日・27日の二日間に渡り、長野市上野のIさんのお住いで
上棟が行われました
9月26日

秋晴れの中、Iさんにもお立ち会いいただき、安全祈願をして工事を開始。
会社で製材した材木たちはクレーンで吊り上げられ、
次々と建てられていきます

胴差(どうさし)を掛け矢(大形の木槌)で叩き、はめこんでいく作業中のY大工さん。


お昼前には、1階部分が出来上がりました

床梁(ゆかばり)を組んでいきます。
大工さんが刻んだ継手(この場合は、梁同士の接合部)や仕口(この場合は、
梁と柱の接合部)をしっかりと合わせ、掛け矢で叩いて固定。
↓ ↓

午後3時過ぎ、きれいに納まっていました
9月27日

翌27日、屋根の垂木(棟木から斜めに架け渡されている部分)をかけて、
夕方5時半過ぎ作業は無事に終了。続いて上棟式に移ります。

午後6時、Iさんご夫妻にも来ていただき上棟式開始です。

家の四隅にお酒、塩、お米をまいて清め、今後の工事の安全を祈願いたしました
これからしばらくの間、大工さんの造作工事が進みます。
~*追記*~
上の写真はお隣の家のベランダから撮影したものが含まれています。
お隣にお住いの方の、ご厚意で上らせていただきました。
この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました
上棟が行われました

9月26日

秋晴れの中、Iさんにもお立ち会いいただき、安全祈願をして工事を開始。
会社で製材した材木たちはクレーンで吊り上げられ、
次々と建てられていきます


胴差(どうさし)を掛け矢(大形の木槌)で叩き、はめこんでいく作業中のY大工さん。


お昼前には、1階部分が出来上がりました


床梁(ゆかばり)を組んでいきます。
大工さんが刻んだ継手(この場合は、梁同士の接合部)や仕口(この場合は、
梁と柱の接合部)をしっかりと合わせ、掛け矢で叩いて固定。
↓ ↓

午後3時過ぎ、きれいに納まっていました

9月27日

翌27日、屋根の垂木(棟木から斜めに架け渡されている部分)をかけて、
夕方5時半過ぎ作業は無事に終了。続いて上棟式に移ります。

午後6時、Iさんご夫妻にも来ていただき上棟式開始です。

家の四隅にお酒、塩、お米をまいて清め、今後の工事の安全を祈願いたしました

これからしばらくの間、大工さんの造作工事が進みます。
~*追記*~
上の写真はお隣の家のベランダから撮影したものが含まれています。
お隣にお住いの方の、ご厚意で上らせていただきました。
この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました

2014年09月22日
須坂市村山で地鎮祭を執り行いました。

21日(日)秋晴れの中、須坂市のKさんのお住まいにて、地鎮祭が執り行われました。
設計は、萌建築設計工房さんです


Kさんご家族、萌建築設計工房の池森さん、弊社スタッフが列席し、
地鎮祭が厳かに始まりました。

はじめに神主さんが参列者を祓い清めて、土地の神様に祝詞を奏上。
大幣(おおぬさ)を振って家の四隅をお祓いしたのち、さらに切幣(きりぬさ:
小さな四角に切った和紙)をまいて四方を祓い清めます。

神主さんの奏でる篳篥(ひちりき)の生演奏が響く中、Kさんご家族、
萌建築設計工房の池森さん、会社スタッフが順番に、玉串を神前に奏上して
土地の安泰と工事の安全を願いました

Kさんのお住まい、いよいよ工事が始まります

2014年09月20日
北堀の現場から ~幅木と四角穴ビスの関係!~
Wさんのお住いの現場から、造作の様子をお伝えします

プラスターボード張りが、現在進行中で行われています。

2階は、ほぼ全室完了で、棟梁のYさんは1階のボード張りの最中。
と、いつものようにブログを進めていますが、今日の主役はこちら
↓ ↓ ↓

巾木(はばき)
巾木は床と壁のつなぎ目に取り付ける細長い横木です。
生活する中でつけられる傷や汚れから、壁面を守る役割があります。

ビス
(Yさんが撮影しやすいようセッティングしてくれました )
)

近年、木工用ボンドで、お手軽に取り付けることの出来るものや
安価なソフトビニール巾木などが多用されるようになりましたが、
弊社では全て大工さんが、刻みから施工まで丁寧に仕上げます。

この巾木を固定するためのビスが「四角穴ビス」です。
通常よく見かけるのは十字のビスだと思いますが、Yさん曰く
「十字ビスに比べて、力がうまく逃げるので、ドライバーが逃げず木を傷めない。」
のだそうです。
調べてみると、ビットが折れにくい。ビスが外れにくく、曲がりやすいところでも
真っ直ぐに打てる。などのメリットがあるようです

こちらがアップの写真。
四角穴ビスで固定された巾木。壁の下地板がしっかりと溝に納まっています
「鎌倉の家は全部手づくりなんだよ。今は中々ないよ。」と棟梁Yさんが
熱く語ってくれました。このような大工さんの技が、鎌倉材木店の
「こだわりの木の注文住宅」を支えてくれています。
造作工事中だから見られる空間~番外編~

手づくり階段の裏側です。
見えなくなるところだからこそ、しっかりと造作するのです


プラスターボード張りが、現在進行中で行われています。

2階は、ほぼ全室完了で、棟梁のYさんは1階のボード張りの最中。

と、いつものようにブログを進めていますが、今日の主役はこちら

↓ ↓ ↓

巾木(はばき)

巾木は床と壁のつなぎ目に取り付ける細長い横木です。
生活する中でつけられる傷や汚れから、壁面を守る役割があります。

ビス

(Yさんが撮影しやすいようセッティングしてくれました
 )
)
近年、木工用ボンドで、お手軽に取り付けることの出来るものや
安価なソフトビニール巾木などが多用されるようになりましたが、
弊社では全て大工さんが、刻みから施工まで丁寧に仕上げます。

この巾木を固定するためのビスが「四角穴ビス」です。
通常よく見かけるのは十字のビスだと思いますが、Yさん曰く
「十字ビスに比べて、力がうまく逃げるので、ドライバーが逃げず木を傷めない。」
のだそうです。
調べてみると、ビットが折れにくい。ビスが外れにくく、曲がりやすいところでも
真っ直ぐに打てる。などのメリットがあるようです


こちらがアップの写真。
四角穴ビスで固定された巾木。壁の下地板がしっかりと溝に納まっています

「鎌倉の家は全部手づくりなんだよ。今は中々ないよ。」と棟梁Yさんが
熱く語ってくれました。このような大工さんの技が、鎌倉材木店の
「こだわりの木の注文住宅」を支えてくれています。
造作工事中だから見られる空間~番外編~

手づくり階段の裏側です。
見えなくなるところだからこそ、しっかりと造作するのです

2014年09月17日
長野市松代で地鎮祭が執り行われました!

長野市松代町で、新築されるMさんのお住まいの地鎮祭が、執り行われました



神主さんが厳かに、祝詞を奏上します。

敷地の四隅には、「四神」と呼ばれる天の四方をつかさどる神々が
祭られているそうです。
東は青竜、西は白虎、南は朱雀で北は玄武。
それぞれの方角で「切幣(きりぬさ)」をまき、祓い清めます。
最後に、榊の枝に紙垂と幣をつけた玉串を捧げて、無事に地鎮祭が終わりました。
地鎮祭は神式・仏式とあり、以前キリスト教式の地鎮祭を執り行ったことも

お施主様のご要望で、どのような形式でも可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。
2014年09月12日
ブラックウォールナット・山桜を使用した上越のお住いⅡ
前回から引き続き、上越のTさんのお住いのご紹介です
Tさんはお仕事柄、木材についてのご見識が深く、新築のお住いは何種類もの
無垢材を随所にご使用になられています。

こちらは離れになっています。 外壁は杉板の横張りです。
外壁は杉板の横張りです。

離れの北側にある窓です。
ここの窓の採光を遮るのはカーテンや障子ではなく、木目が美しい
ケヤキ一枚板の引戸です。
写真右に本宅とつながる渡り廊下が、ちょっとだけ見えます。

こちらの和室の床材は、ケヤキと山桜。下地が見えている部分に畳がはいります。
Tさんのお住いの工事、まだすべて終わっていません。
畳が入った和室が、どのように様変わりするのかも楽しみです

天井に立派な梁が
これは古民家の梁材等を再利用したものです。
ここでも材のもつ色目の違いが、アクセントになっています。

ケヤキ梁にふくろうと小槌が細工してあるのがわかりますか?
梁の傷を隠すためのものだったそうですが、はじめから計算されていたように
しっくり納まっています。
愛嬌のあるフクロウの表情が何ともいえません
今回ご紹介しましたTさんは、上杉謙信の居城、春日山城の東山裾に
ご新居を構えました。ここはTさんの念願だった場所なのだそうです。
窓の位置も、春日山を毎日眺められるように設計されているそう。
昔からの夢を叶えられたTさん、うらやましい限りですね
*鎌倉材木店では*
自社で製材した品質の良い木材を、今回のT様の案件のように、
安価でお客様にお届けしております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
電話/026-221-5375
Fax/026-221-5386
http://kama-kura.com/inquiry/
※販売・納品は当社より200km範囲での対応となりますので、ご了承ください。

Tさんはお仕事柄、木材についてのご見識が深く、新築のお住いは何種類もの
無垢材を随所にご使用になられています。

こちらは離れになっています。
 外壁は杉板の横張りです。
外壁は杉板の横張りです。
離れの北側にある窓です。
ここの窓の採光を遮るのはカーテンや障子ではなく、木目が美しい
ケヤキ一枚板の引戸です。
写真右に本宅とつながる渡り廊下が、ちょっとだけ見えます。

こちらの和室の床材は、ケヤキと山桜。下地が見えている部分に畳がはいります。
Tさんのお住いの工事、まだすべて終わっていません。
畳が入った和室が、どのように様変わりするのかも楽しみです


天井に立派な梁が

これは古民家の梁材等を再利用したものです。
ここでも材のもつ色目の違いが、アクセントになっています。

ケヤキ梁にふくろうと小槌が細工してあるのがわかりますか?
梁の傷を隠すためのものだったそうですが、はじめから計算されていたように
しっくり納まっています。
愛嬌のあるフクロウの表情が何ともいえません

今回ご紹介しましたTさんは、上杉謙信の居城、春日山城の東山裾に
ご新居を構えました。ここはTさんの念願だった場所なのだそうです。
窓の位置も、春日山を毎日眺められるように設計されているそう。
昔からの夢を叶えられたTさん、うらやましい限りですね

*鎌倉材木店では*
自社で製材した品質の良い木材を、今回のT様の案件のように、
安価でお客様にお届けしております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
電話/026-221-5375
Fax/026-221-5386
http://kama-kura.com/inquiry/
※販売・納品は当社より200km範囲での対応となりますので、ご了承ください。
2014年09月10日
ブラックウォールナット・山桜を使用した上越のお住いⅠ
今回ご紹介するのは上越在住のお客様、Tさんのお住いです
自宅を新築するにあたり、当社の材木を床・建具・家具に
使用していただいております。

玄関から室内に通じるドアはブラックウォールナットと、山桜を使用。
山桜は当社で丸太から製材したものです。
山桜は製材して2~3ヶ月たつと、赤くなるそう
このドアは取り付けてから、5ヶ月程経っているので赤みを帯びてきています。

こちらは玄関脇の、山桜を使用したデザイン壁。
ゆるくかかったアールが、材の美しさを引き立たせています。
山桜は年々赤みが増し、とても美しい色に落ち着いていくそうです。
無垢材の良さはこんなところにあるのかもしれません

ブラックウォールナットの階段。

玄関左のリビングの壁は珪藻土。
床材はブラックウォールナット。天井・梁は杉材、一部に山桜を使用しています。
三種類の異なる材の対比が楽しめる、木にこだわったお住いを
象徴するかのようなリビングです。

2階リビングの床はブラックチェリー。
壁の一部に山桜を使用しています。


写真:上 トイレ戸棚
写真:下 キッチン戸棚
両方ともブラックウォールナットを使用し、
部屋サイズに合わせてつくられた造作戸棚です。
ウォールナットの独特の木目と、重厚感あふれる色合いが
とても美しい家具です。
上の写真、ここがトイレとは思えないですよね

リビングの造作家具は山桜を使用。フローリングはブラックウォールナット。
あえて床置にせず壁面に造り付けることで、お互いの木の美しさを
引き立たせあっています。
合板等は一部の下地材として使用したのみで、塗装もすべて自然素材のもの。
木のもつあたたかみ、美しさが、最大限に引き出されたお住いです
次回は離れの紹介をいたします

自宅を新築するにあたり、当社の材木を床・建具・家具に
使用していただいております。

玄関から室内に通じるドアはブラックウォールナットと、山桜を使用。
山桜は当社で丸太から製材したものです。
山桜は製材して2~3ヶ月たつと、赤くなるそう

このドアは取り付けてから、5ヶ月程経っているので赤みを帯びてきています。

こちらは玄関脇の、山桜を使用したデザイン壁。
ゆるくかかったアールが、材の美しさを引き立たせています。
山桜は年々赤みが増し、とても美しい色に落ち着いていくそうです。
無垢材の良さはこんなところにあるのかもしれません


ブラックウォールナットの階段。

玄関左のリビングの壁は珪藻土。
床材はブラックウォールナット。天井・梁は杉材、一部に山桜を使用しています。
三種類の異なる材の対比が楽しめる、木にこだわったお住いを
象徴するかのようなリビングです。

2階リビングの床はブラックチェリー。
壁の一部に山桜を使用しています。


写真:上 トイレ戸棚
写真:下 キッチン戸棚
両方ともブラックウォールナットを使用し、
部屋サイズに合わせてつくられた造作戸棚です。
ウォールナットの独特の木目と、重厚感あふれる色合いが
とても美しい家具です。
上の写真、ここがトイレとは思えないですよね


リビングの造作家具は山桜を使用。フローリングはブラックウォールナット。
あえて床置にせず壁面に造り付けることで、お互いの木の美しさを
引き立たせあっています。
合板等は一部の下地材として使用したのみで、塗装もすべて自然素材のもの。
木のもつあたたかみ、美しさが、最大限に引き出されたお住いです

次回は離れの紹介をいたします

2014年09月08日
鬼無里の現場から。~階段の造作~

鬼無里のMさんのお住いから、階段の造作工事の様子です。

8月末、階段の造作が始まっていました。
段板の上にボンドが置いてあります。ここが1段目です
↓ ↓

アップにしてみました。

階段の側板です。
縦と横に彫り込みが入っているのがわかりますか?
横の彫り込みに段板、縦の彫り込みには蹴込み板を差し込みます。
この刻みも、大工さんが手でおこないます

※段板(だんいた)=階段の足をのせる部分の板のこと
※蹴込み板(けこみいた)=段板と段板の間に垂直に立てた板のこと

階段を2階から見たところ。
Mさんのお住いは、「折り返し階段」になっています。

2階から撮影中にH大工さんを発見しました!
こんなところでお昼寝・・
 ではありません。
ではありません。1段目の階段の裏側で一生懸命作業中です


撮影が終わる頃、A大工さんが「あっちの部屋から出られるよ。」と
教えてくれました。
段ボールが片づけられた窓には踏み台が!ありがとうございます

今日は玄関ではなく、2階の足場から帰りました。
Mさんのお住いの造作は、これからも続きます

2014年09月05日
上野のお住い ~大工さんによる手刻みの作業場~
長野市上野のIさんのお住いの現況です

8月8日、配筋が終了しました。

基礎工事も完了です。
次はいよいよ土台敷、そして上棟となります

こちらが出番待ちの材木たち。

そのため社屋の裏にある作業場で、大工さんたちは毎日
材木の刻みに追われています

“墨付け”がされた材木。
この“墨付け”された箇所を、のみや鋸(ノコギリ)で切ったり、
削ったりしてゆく作業を「刻み」といいます。

これが“墨付け”の道具、「墨つぼ」と「墨さし」です。

梁に化粧がされています
このような化粧を「釿(ちょうな)はつり」と言うそうですが、
今回「釿(ちょうな)」は使用していないそうです。
亀甲(きっこう)という、はつり方法に似ていますが
M大工さんいわく「やり方は企業秘密だよ」と、はぐらかされてしまいました

木の表面を“はつる(削りとる)”ことで木目に動きが出て、
ひと味違う雰囲気の梁となりました。

きちんと並べられたM大工さんの大工道具たち。
近年、木材の加工はプレカットが主流となっていますが、
木造住宅で無垢材を取り扱う当社では、大工職人さんが1本1本
材の性質を見ながら手刻みをします。
古くから受け継がれてきた「手刻み」。時間と手間はかかりますが
一つ一つ丁寧に仕上げる伝統工法、大切にしたいですね
※プレカット=コンピューターと機械による、柱や梁の接ぎ手・仕口加工のことです。


8月8日、配筋が終了しました。

基礎工事も完了です。
次はいよいよ土台敷、そして上棟となります


こちらが出番待ちの材木たち。

そのため社屋の裏にある作業場で、大工さんたちは毎日
材木の刻みに追われています


“墨付け”がされた材木。
この“墨付け”された箇所を、のみや鋸(ノコギリ)で切ったり、
削ったりしてゆく作業を「刻み」といいます。

これが“墨付け”の道具、「墨つぼ」と「墨さし」です。

梁に化粧がされています

このような化粧を「釿(ちょうな)はつり」と言うそうですが、
今回「釿(ちょうな)」は使用していないそうです。
亀甲(きっこう)という、はつり方法に似ていますが
M大工さんいわく「やり方は企業秘密だよ」と、はぐらかされてしまいました


木の表面を“はつる(削りとる)”ことで木目に動きが出て、
ひと味違う雰囲気の梁となりました。

きちんと並べられたM大工さんの大工道具たち。
近年、木材の加工はプレカットが主流となっていますが、
木造住宅で無垢材を取り扱う当社では、大工職人さんが1本1本
材の性質を見ながら手刻みをします。
古くから受け継がれてきた「手刻み」。時間と手間はかかりますが
一つ一つ丁寧に仕上げる伝統工法、大切にしたいですね

※プレカット=コンピューターと機械による、柱や梁の接ぎ手・仕口加工のことです。
2014年09月02日
造作工事中だから見られる空間。~北堀のお住い~
長野市北堀のWさんのお住いの造作工事現場です
7月29日

屋根は陶器瓦を使用。写真の瓦の形状が違うのがわかりますか?
一番外側の瓦は雨が拡散しやすいように、中側の瓦は積雪が一気に落下しないように
デザインされているそうです
8月11日

今回は「造作工事中だから見られる空間。」
そんな場所をカマクラなりに探してみました

Wさんのお住いは高気密高断熱の当社独自、シーズンレス工法。
硬質発泡ウレタンが吹き付けられています。
玄関の扉は、LIXIL社の「断熱玄関ドアジエスタ」のもの。

フローリングが施工される前の床下地です。
この下にも断熱材が敷き詰められています
8月28日

こちらは「足場」です。
はしごが苦手なカマクラが、2階の撮影をする時は
もっぱらこの「足場」を利用しています

洋室から浴室までの眺めです。
洋室→ウォークインクローゼット→洗面室→トイレ→浴室
この写真の中の空間は、これだけの部屋に分かれるのです。
当然ですが完成後は壁に仕切られ、見えなくなる空間です

こちらはパントリーから浴室までの眺めです。
現在は広めの廊下みたいですが、キッチン→脱衣室→浴室
と分かれます。
足場は工事が終われば撤去され、床下地・硬質発泡ウレタン・骨組みは
それぞれフローリングや壁材が施工されると見えなくなります。
これからも「今だから見られる空間。」 を
わかりやすくお伝えしていけたらと思います

7月29日

屋根は陶器瓦を使用。写真の瓦の形状が違うのがわかりますか?
一番外側の瓦は雨が拡散しやすいように、中側の瓦は積雪が一気に落下しないように
デザインされているそうです

8月11日

今回は「造作工事中だから見られる空間。」
そんな場所をカマクラなりに探してみました


Wさんのお住いは高気密高断熱の当社独自、シーズンレス工法。
硬質発泡ウレタンが吹き付けられています。
玄関の扉は、LIXIL社の「断熱玄関ドアジエスタ」のもの。

フローリングが施工される前の床下地です。
この下にも断熱材が敷き詰められています

8月28日

こちらは「足場」です。
はしごが苦手なカマクラが、2階の撮影をする時は
もっぱらこの「足場」を利用しています


洋室から浴室までの眺めです。
洋室→ウォークインクローゼット→洗面室→トイレ→浴室
この写真の中の空間は、これだけの部屋に分かれるのです。
当然ですが完成後は壁に仕切られ、見えなくなる空間です


こちらはパントリーから浴室までの眺めです。
現在は広めの廊下みたいですが、キッチン→脱衣室→浴室
と分かれます。
足場は工事が終われば撤去され、床下地・硬質発泡ウレタン・骨組みは
それぞれフローリングや壁材が施工されると見えなくなります。
これからも「今だから見られる空間。」 を
わかりやすくお伝えしていけたらと思います