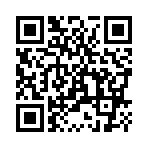2008年05月20日
こちらも、大工さんの造作工事が進んでいます
4月22日(火)
 川中島で工事が進むIさんの家
川中島で工事が進むIさんの家
すこし写真撮影に自信がついてきた営業カスガさんが、様子をうかがいにやってきました。
 外観は、タイベック(外装下地用防湿・防水シート)が見えている状態。
外観は、タイベック(外装下地用防湿・防水シート)が見えている状態。
カスガさん、営業アライさんに対抗して、さりげなく花を入れた構図に挑戦しています
 こちらは、菜の花一本。。
こちらは、菜の花一本。。
コレを見たアライさん、不敵な笑みを浮かべ、ぼそっと一言
「フッ、まだまだだな...」

さて、中では大工さんたちが造作工事を進めていました。
 すべての窓にサッシが入り、
すべての窓にサッシが入り、
 壁にはまぐさや間柱が施工され、天井はプラスターボードで覆われていました。
壁にはまぐさや間柱が施工され、天井はプラスターボードで覆われていました。
5月17日(火)
 それからおよそ1ヵ月後。
それからおよそ1ヵ月後。

ほぼすべての壁に断熱材が充填されていました。

和室の壁には、左官下地のグレー色のボードが張られています。
 階段も途中まで施工済み。
階段も途中まで施工済み。
当社ではほとんどの場合、大工さんがひとつひとつ寸法を見て刻んで作ります。
 表わしの太い柱は、作業中にキズが付かないように包んで養生。
表わしの太い柱は、作業中にキズが付かないように包んで養生。
Iさんの家の造作工事は、まだしばらく続きます
 川中島で工事が進むIさんの家
川中島で工事が進むIさんの家
すこし写真撮影に自信がついてきた営業カスガさんが、様子をうかがいにやってきました。
 外観は、タイベック(外装下地用防湿・防水シート)が見えている状態。
外観は、タイベック(外装下地用防湿・防水シート)が見えている状態。カスガさん、営業アライさんに対抗して、さりげなく花を入れた構図に挑戦しています

 こちらは、菜の花一本。。
こちらは、菜の花一本。。コレを見たアライさん、不敵な笑みを浮かべ、ぼそっと一言
「フッ、まだまだだな...」

さて、中では大工さんたちが造作工事を進めていました。
 すべての窓にサッシが入り、
すべての窓にサッシが入り、 壁にはまぐさや間柱が施工され、天井はプラスターボードで覆われていました。
壁にはまぐさや間柱が施工され、天井はプラスターボードで覆われていました。5月17日(火)
 それからおよそ1ヵ月後。
それからおよそ1ヵ月後。
ほぼすべての壁に断熱材が充填されていました。

和室の壁には、左官下地のグレー色のボードが張られています。
 階段も途中まで施工済み。
階段も途中まで施工済み。当社ではほとんどの場合、大工さんがひとつひとつ寸法を見て刻んで作ります。
 表わしの太い柱は、作業中にキズが付かないように包んで養生。
表わしの太い柱は、作業中にキズが付かないように包んで養生。Iさんの家の造作工事は、まだしばらく続きます

2008年04月02日
上棟後3週間→床の下地施工とサッシの取り付け
2月下旬に上棟した川中島のIさんの家

その後の現場の様子をお伝えします。
3月15日(土)
屋根工事が終わり、透湿防水機能をそなえた白いシート"タイベック"が
張られたIさんの家。
天井のほうは、見上げると美しい小屋裏が見える状態です。
化粧の梁や柱(室内に表わしになる材)は、キズがつかないよう養生のシートで
覆われたままでした。
3月27日(木)

それからおよそ2週間後。前とのちがいにお気づきでしょうか?
 そうです、サッシが入っていました。
そうです、サッシが入っていました。施工はずいぶん終わっていますが、この日も
大工のケンイチさんがサッシをはめ込むため
の作業中。

敷地には、たいへん立派な柿の木が立っています。
「おいしい柿ができる木だから切らないでほしい」というI家のおじいさまの
希望で、家側にはり出していた枝だけ切り落とし、木自体は残すことに。

中も、様変わりしていました。

床の断熱材を入れ、コンパネ(床の下地材)を張る作業をしているよう。

横から見た断面は、こんなかんじ。
根太の間に断熱材を隙間なく敷き詰め、その上にコンパネを張るのです。
 大工のアシザワさんが、差し金を使って
大工のアシザワさんが、差し金を使ってなにやらを測っているところ。
差し金というのは、シンプルな造りながら非常に
よくできた大工道具で、昔は、使いこなせれば、
これ一本で家が建つ、といわれたのだとか。
水平も垂直も出せ、ルートの計算もでき、尺貫法
とメートル法も一発で換算できる...
差し金も含め、大工道具は、奥深い。。

2F小屋裏の柱の高いところにちらっと見える白いもの、あれは上棟の証
でもある御幣棒(おんべぼう)です。
これは、お施主さんや大工さんなど、家づくりに関わった人々の名や、
上棟した年月日などを書き付ける棟札代わりでもあります。
これからずっと小屋裏にあって、静かに家を見守ります。

いつもながら、サッシが入るとぐぐっと家らしさが増します

3月中旬以降、ずいぶんと春めいてきて(昨日は雪が見えましたが...)、
断熱材の入っていない現場もずいぶん作業しやすい気候になってきました。
着々と工事は進んでいます

2008年02月25日
川中島にて、上棟しました
23日の土曜日は、川中島で新築されるIさんの家の上棟の日でした

この間若里のKさんの家の写真を撮ってきて、無情にもわたしに
ダメ出しされた営業カスガさん、「こんどは怒られないように」と
かなり気を入れて撮ってきたよう。
そのありがたい写真で、さっそく上棟風景をご紹介です。
作業は、朝8時から始まりました。
11時前には、このとおり2F部分の作業へ。
アシザワさんです。
そのアシザワさんが、真剣な面持ちで
じっと見ているのが、
こちらの、図板(ずいた)。
以前、若里のKさんの家の上棟風景を紹介した折にも、ちらっと
説明しましたが、これは昔ながらの大工さんにとっての平面図。
大工さんたちはこれでひとつひとつの柱の位置を確認しながら、
墨付け(材木に番号をふっていく作業)をしてゆきます。
手際のよい作業で、2F部分の柱が次々に立てられていきます。
クレーンのすぐ横にいるのが、I邸の現場代理人ヨシダさん。
お昼をはさんで、午後2時半ともなると、屋根のかたちが見えてきました。
柱や小屋束に対して垂直方向に、母屋がかけられていきます。
さらに屋根のてっぺんにかける棟木が上がり、無事に上棟しました

軍手をしてアシザワさんを手伝っているのは、Iさんの家の設計を担当した設計士のセトさんです。
棟は上がりましたが、作業はまだ続きます。
母屋を施工したら、次はその上に垂木をかけていきます。
写真は、大工さんたちみんなで分担して釘を打って、固定しているところ。
午後4時頃になると、にわかに大粒の雪が舞いはじめました

当初の予定では、野地板(屋根の下地材)まで張るということでしたが、雪が激しさを増してきて、足元が滑りやすく危ないという現場の判断により、垂木の施工まででこの日の作業は終了。
Iさんご家族と大工さんたち、会社のスタッフで、上棟式がとり行われました。
新しい住まいの骨組みの建ち姿をみて、とても感慨が深い様子だったIさんとご家族。
作業が無事に終わり、大工さんたちも、ほっとひと安心です。
こちらのIさんの家は、6月の完成をめざし工事が進められていきます

2008年02月16日
鳥とお花で春の気配
土曜日の静かな朝、川中島にて1週間後に上棟を控えるIさんの家の
現場に現れたのは、営業アライさん。
冬になって植物が休眠中のためか、このところカメラマン魂がすっかり
なえていた感のあるアライさん。
が、今日は春の兆しを発見したようで、ひさびさに「これはゲイジュツだ」
なんていいながら、意気揚々とカメラを持ち帰ってきました。
聞けば、"ウグイス"を撮ってきたとのこと。
そして出てきた写真がこちら↓
「...?アライさん、どこにウグイス?」
「知らない、どっかにいるんじゃねえ?」
そういわれて、よーーく見てみると、...いました。たしかに。
みなさま、わかりますでしょうか?


次の写真は、ちょっと"ウグイス"に寄っています。
でも、あやしい人間が近づいてくるのを察知して、きびすを返したところを
捉えたらしく、写っているのは後ろ姿。
...というか、この色からして、この鳥ウグイスじゃないですよ、アライさん。
 羽が抹茶色のような色彩で(この色はウグイス色とは呼ばないそうなので)、しばしば梅と対でイメージされるこの鳥は、ウグイスではなく"メジロ"。
羽が抹茶色のような色彩で(この色はウグイス色とは呼ばないそうなので)、しばしば梅と対でイメージされるこの鳥は、ウグイスではなく"メジロ"。目のまわりが白く縁取られていることから、その名がついたと言われます。
(写真は、ウィキペディアより)
 ちなみに、こちらがウグイス。
ちなみに、こちらがウグイス。色は、かなり地味です。
でもこの色が、ほんとうの「ウグイス色」なのだそう。
ふだんはほとんど藪の中にいる上、羽の色もまわりと同化しがちなので、たとえすぐ近くで鳴き声がしても、その姿を捉えるのがなかなかムズカシイ鳥。
"ウグイス"に遭遇したアライさん、現場の一隅に春の気配を見つけました。
オオイヌノフグリです。
でも、オオイヌノフグリの毛がふさふさした葉っぱの方にピントが合って、
肝心の花が完全なピンボケ。
ゲイジュツ作品を撮るには、まだまだリハビリが必要なようです...
会社の裏の作業場では、Iさんの家を手がけるアシザワ大工さんが、刻み作業中。
ちょうどこのときは、席を外していたようで、刻みかけの材が静かに横たわっています。
タバコの箱3つ分はある、化粧の大きなヒノキの柱。
タバコの箱、というのはあまり印象よろしくないかもしれませんが、
いかに太い材か、というのを分かっていただくためのアライさんの
工夫なのであしからず。。
傍らには、すでに刻まれた材が、所狭しと積み上げられています。
上棟まであと1週間。刻み作業も追い込みです

2007年11月26日
晩秋の地鎮祭
しばらく続いていた寒さも緩み、きれいに晴れ渡った日曜日

川中島で新築を予定しているIさまの家の地鎮祭が執り行われました。
神主のトミオカさんが四方の神さまに切幣を撒いて、祓い清めます。
それを終えると、玉串奉奠(たまぐしほうてん)。
神主さんから受け取った玉串(榊)をうやうやしく捧げ、神さまに工事の無事と、
建てる家のご加護を願います。
お施主のIさま、それから奥さま。
幼い息子さんと娘さんは、それぞれ、お父さんとお母さんにお祈りの仕方を
教わりながら、玉串を奉納しています。
初めての儀礼的なお祈りに、こころなしか気恥ずかしそうな様子です。
そしてさいごに、奥さまのご両親が玉串を神さまに捧げます。
青空の下、みんなで笑顔で記念撮影。
こちらのIさまの家は、これからしばらくして基礎工事がはじまり、
来春の完成を目指す予定です