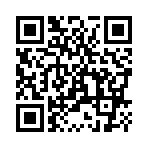2008年11月17日
住宅施工例に、川中島の2世帯住宅をアップしました
鎌倉材木店ホームページに、先日お引渡しになった川中島の2世帯住宅
Hさんのお住まいの様子を掲載しました

㈱鎌倉材木店ホームページ 一般住宅施工例 長野市川中島H邸
ヒノキ材をふんだんに使った、和風デザインのお住まいです

ぜひごらんください☆
2008年10月29日
川中島の2世帯住宅、完成しました
長野市川中島で建て替え工事が進んでいたHさんの2世帯住宅

以前は、築150年ほどの古民家。(以前の様子)
新しいお住まいがこのほど完成し、昨日無事にお引渡しとなりました。
無垢材をふんだんに使った広い玄関ホール。
壁は、塗りの壁です。
南面に配されて、陽が明るい親世帯のLDK。
リビングは、暮らしやすさを考えて畳敷きにしました。
格調の高さが漂う、2間続きの和室。
2F、若世帯の居住スペースのキッチン。
ダイニング・リビングは、親世帯と同じく南面にあって、明るく暖かな
空間になっています

こちらの川中島H邸の詳しい様子は、後日当社ホームページの
一般住宅施工例でご紹介します

お楽しみに☆
2008年10月01日
大工さんの造作工事が、終盤です
長野市川中島で工事が進む2世帯住宅、Hさんのお住まい

腰壁と塗り壁用の下地材がすでに施工済み。
現場の一隅では、大工のヤマグチさんとコウメイさんが忙しく仕事中。
大工さんたちの造作工事も、いよいよ終盤です

ここは、ダイニングキッチンの一角。
間仕切りで仕切ることができる設計です。
H邸の完成まで、あともうすこしです

2008年07月30日
川中島にて、大工さんの造作工事(+アライさんがみつけた擬態)
川中島で建て替え工事が進む2世帯住宅、Hさんのお住まい

ひさびさに出ました、"花を入れた構図"。
営業アライさん、気分がノッていたようです

中に入ると、玄関のところで大工のコウメイさんが、床板(フローリング)を
張っていました。
前回と比べると、ずいぶん造作工事が進んだ様子。
フローリング材には、ナラの無垢材を使っています。
H邸も、当社オリジナルのシーズンレス工法を採用した、高断熱・高気密住宅。
壁は硬質発泡ウレタン吹きつけが終わって、
部分的には、フローリングをはじめ、壁下地であるプラスターボードまで施工済み。
2階居室は、大工さんの造作工事が終盤にさしかかっています。
いずれは外から見えなくなってしまう場所も、ひとつひとつが大工さんによる丁寧な手仕事なのです

☆営業アライさんの自称"サービス(?)ショット"☆
訝しく思ってじっくり見ると、そこにはある生き物が...
もうちょっと上手に擬態しないと。
アライさんに見つかるようでは、鳥に食べられてしまうよ。
2008年07月03日
床組み→FRP防水作業や軒天施工
今日は、川中島で工事が進むHさんのお住まいの様子です

6月11日(水)
この日、営業アライさんがH邸の現場を訪れたときには、
大工のコウメイさんが、1Fの床組みを施工中でした。
写真右上には、うずたかく積まれた床用断熱材が見えます。
整然とした床下です。
7月1日(火)
そして、きれいに晴れたおとといの現場の様子

窓が入ると、一気に住まいらしさが増します

2Fの方から、工事は着々と進んでいます。
バルコニーは、耐水性が必要な場所。雨雪で濡れてもダメージを受けないよう、このような特殊な防水加工を施します。
地道かつ、精度の要求される作業です。。

2008年06月02日
上棟1ヵ月後の現場の様子と、古材の製材風景

未だ屋根裏が筒抜けに見えるところもありますが、
すでに床の下地が施工され、1階と2階がぴっちり仕切られているところもあります。
この板は、ヒノキ材。
ヒノキ材は、湿気による腐食に強いため、
風雨にさらされるこのような場所の施工には
適した材なのです。
微妙にぐらつくはしごを上って、2階へ。
紙垂(しで)が静かに風に棚引いていました。
大工さんによる作業は、これからまだまだ続きます

このたびの家の建て替えにあたり、かつてのお住まいの材を一部使うことになっていて、先日その古材の製材(木取り)が行なわれました。
(製材風景写真:設計士ワダさん)
江戸時代末期あたりから、鴨居梁として使われてきたこのケヤキ材は、
黒くなっていて木目がまったく見えません...
そのため、まずは木目が見える程度にうすーく材の表面を削ります。
数ミリ表面を削り落とすと、このとおり、やわらかな色合いの木肌が現れました

製材機の刃を傷めるため、即、取り外します。
長い間使われていた材なので、割れや虫食いもところどころに見られます。。
ほぞの部分などを切り落としたこの材は、床の間の框として、
さらに命をつなぐことになります

余った部分は、仏間の敷居用に製材。
Hさんの新しい住まいで、これらの古材がどんな風に生きるのか、乞うご期待です☆
2008年04月28日
雨の土曜日、川中島での上棟風景
聖火リレーで、長野市が長野市のようでなくなっていた先週土曜日。
川中島の西友近くでは、朝8時からH邸の上棟作業がはじまっていました

Hさんの新しいお住まいは、和風デザインの2世帯住宅。
当社オリジナルのシーズンレス工法(高断熱・高気密仕様)を採用します。
大きな松の木が見守る中、作業は着々と進みます。
ヤマグチさんの指示のもと、応援に駆けつけた大工さんたちがそれぞれ、
仕事に精を出しています。
クレーンで吊り上げられた大きな梁を、慎重に所定の場所へはめ込む様子。
材木は、とにかく大きくて重いので、作業中は気が抜けません

午後は、2階部分の組み立て作業が続いていました。
あらかじめ組まれて、現場の傍らに積まれている材を、順番にクレーンで
吊るして2階へ運び上げ、施工します。

大工さんたちはみんな上下に雨具を着込み、長靴を履き、足場も視界も悪い中での作業です。。
棟木が上がり、上棟式がはじまったのは、日も傾きかけた午後6時ごろ。

こちらのH邸は、今年10月末の完成を目指して工事が進められます。
2008年03月27日
旧家屋解体→とこしずめのみまつり(地鎮祭)
川中島にて建替えをされるHさんのお住まい

旧家屋の解体作業から昨日の地鎮祭の様子をご紹介します。
3月11日から1週間ほどかけておこなわれた解体作業。
現在は、ひと昔前のように重機で一気に破壊する、ということはせず
種類ごとに分別しながらの手作業です。
「すごい写真になっちゃったよ」と営業アライさん。
どうやら、屋内に充満し光が乱反射した土ぼこりが写りこんだ様子...
それはさておき、特筆すべきはあの曲がりを巧みに組み込んだ大きな梁。
築150年というH邸(「150年前といえば"安政の大獄"の頃」 byアライメモ)。
当時は大きな機械もなく、こういう材を使わざるをえなかった、とはいえ、
すごい技です。
古民家のこういう姿には、いつもながら、ぞくぞくっとします。。
広いお座敷があったため、畳もうず高く積まれています。
数日後、屋内の片づけがひと段落したところで、屋根を取り除いていきます。
ショベルカーを使って少しずつ崩し、
下に落とされたもともとの屋根材である藁や、それを覆っていたトタンを
材料ごとにえり分けながら回収。
それにしても立派な小屋裏。
太めの材には、手斧削り(ちょうなはつり:手斧という大工道具で丸太のまわり
を削ること)の跡が見えます。
古民家の自然にゆるく曲がった線でできた空間には、どこかほっとする
佇まいがそなわっているような気がします。
さらにその数日後。
解体作業はすべて終わりました。
そして昨日。
小雨が降る中、とこしずめのみまつり(地鎮祭)がとり行われました。
敷地の一隅にそびえる大きな松の木も、その様子を見守っています。
無事と安全を祈って神様に玉串を捧げます
<玉串奉奠(たまぐしほうてん)>。
これから秋頃の完成に向けて、工事が進められます

2008年03月06日
川中島にて、解体に際しての清祓いの儀
長野市川中島にあるHさんの家

聞けばこの家は、江戸時代に真田家の剣術の指南役として仕えたH家5代目
御当主が、内弟子たちに手伝ってもらって造り上げたとのこと。
歴史あるお住まいですが、さすがに生活に不便もあることから、このたび10代
目にあたるHさんが建替えをする運びとなりました。
何代にもわたって住み継がれた家というだけあって、風格がちがいます。。
来週はじまる解体工事に先立ち、今日の午前中に清祓いがとり行われました。
清祓いというのは、いわば、今まで住んできた家と、そこでの生活や家族を
お守りくださった神さまたちに感謝する儀式のこと。
庭の大きな樹木を切り倒す際にも、行われます。
太鼓を叩きながら
祝詞をあげます。
など、よくないものが宿りやすいとされる
水まわりを中心に切幣(きりぬさ)をまき
祓い清めます。
トミオカさん、いつも以上に豪快な撒きっぷりです。。
このようにして清祓いを終え、
地鎮祭のときと同じように、玉串を神さまに奉ります。
まずはお施主さまが玉串を捧げ、今までのご加護に感謝しお祈り。
清祓いの儀は、このようにして滞りなく無事に終わりました

ちなみに、家のすぐ脇に佇む大きな木は"黒松"で、樹齢はおよそ350年とのこと。
先人の方々の想いが染みこんだ家を取り壊し、建て直すというのは大きな
決断だったと思います。
これから先、この家と同じように長く住み継いでいってもらえるような家づくり
を目指し、まず来週から、解体工事がはじまります