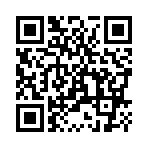2007年11月30日
高田のU邸の上棟式の様子
日が落ちはじめた夕方4時半すぎには上棟を終え、5時前には施主のUさん
ご家族、大工さん、会社のスタッフが揃って上棟式をおこないました。
施主のUさま、棟梁のハラダさん、設計担当のワダさんがそれぞれ、酒と塩と米を
撒き、家の四隅を祓い清めます。
営業アライさんが「ストロボが効かなかったよ」とつぶやいていましたが、
たしかに写真が暗いこと。。
みんなで、上棟の無事を感謝し、今後の建築作業の安全を願います。
U家のご子息コウキくんも、代理人のウラノさんに倣って手をぱちぱち。
それからお神酒で乾杯します。
ん?コウキくんも紙コップ片手に、順番待ち?
お神酒を注いでもらったコウキくん、コップを傾けて、どこまで中身を
こぼさずに耐えられるか、実験中(?)です

こういう試みをしたい気分、よくわかる気がします...
唄い手は棟梁のハラダさんと、手伝いで来ていた
アライさんと、セキグチさん。
アライさんは、善光寺木遣り北信流の保存会で
積極的に活動していて、師範でもあります。
セキグチさんは、30歳前の若い大工さん。
少し前に定期的に行なわれている練習会に
参加したばかりで、「こんなにすぐ機会が巡って
くるなんて...」と恐縮している様子だったけれど
若い世代がこういう伝承文化を継承していると
いうのは、ほんと、頼もしいです。
今朝の現場の様子。
青空の下、ハラダさんとハラヤマさんが屋根の野地板を施工していました

上棟式の後、施主のUさんはこんなふうにお話くださいました。
「感想は、いうなら2つ。"すごい"と"感動した"です」。
「すごい、というのは、自分が建築という分野のことを全然知らず、どう
したらこういうふうに造れるのか、まったく想像がつかない世界なので、
建物を目の前にして、ただただ、"ほんとうに、人の手でこういうものが
できるんだー"と驚いているってことです。しかも一日で、こんなふうに
建つなんて。木遣りも聞いたのは初めてで、家の姿が見えていた感動と
あいまって、ぞくっとしました」。
すこしずつ出来上がってくる家の様子を、日々楽しみに見ていただ
ければと思います

来春の完成をめざし、これから冬の間工事が進められます。
2007年11月29日
高田で上棟作業中です
11月27日、高田のUさまの家の新築予定地。
この現場の棟梁ハラダさんと一緒に仕事をするハラヤマさんが、基礎の
上に土台を敷き、梁と柱などを組んで、上棟に向けての準備を進めて
いました。
そして今日が、上棟の日。
曇っていて肌寒くはありますが、幸いなことに雨や雪ではありません

足場も組まれて、準備万端です。
午前8時前。
大きなクレーンや大工さんたちに、ものめずらしいものを見るような眼差しを
送りながら行きすぎる通学途中の小学生たちの列がひと段落したところで、
安全祈願。
お神酒を一口いただきます。
そしたらさっそく作業開始。
さえぎるものがない住宅街では、このクレーンの腕が現場の目印。
だいたいの場所さえつかんでいれば、地図がなくても現場にたどりつけ、
なかなかに便利です。
お手伝いの大工さんも、営業のカスガさんも、これで場所を見つけたそう。
大工さんたちが、クレーンを操るタケダさんに手で合図を送りながら、
部材をぴったりの位置に誘導します。
代理人のウラノさんと、棟梁のハラダさんが、クレーンの先に部材を固定し、
ゆっくり慎重に立てられ、
持ち上げられて移動します。
低位置にきたら、土台と柱の仕口(接合部)を確認し、
梁の上にいるハラヤマさんが、掛け矢(木槌)で叩いてしっかりはめ込みます。
掛け矢で木を打つ音が、現場周辺に響き渡ります。
大きな音ですが、木と木がぶつかり合う音は不思議と耳障りではない気がします。。
お昼には、2階部分の構造材が組み上げられはじめていました。
今日の午後5時頃には上棟作業を終え、上棟式が執り行われる予定です

2007年11月27日
地盤改良工事の様子
若宮で家を新築するMさまの建設予定地で、地盤改良工事が行なわれています。
昨日の朝はめずらしく霧に包まれ、景色がずいぶんもやもやしていました。
地盤改良工事、というのは、家を建てるには地盤がゆるく、不同沈下などの
恐れがある土地を補強して、丈夫にする工事のこと。
工事の方法は、大別すると場合に応じて2パターンがあります。
(以下、NPO法人住宅地盤品質協会のホームページを参考)
ひとつは、表層地盤改良。
セメント系の土質固化材と現地の地盤の土を混ぜあわせて固めながら
基礎の下に、面状に敷き詰めることで、地盤を強化する方法です。
多くの場合、軟弱な地盤の層が地表から2mほどまでだと、この方策が
とられます。
もうひとつは、柱状地盤改良。
今回Mさまの土地は、軟弱地盤層が5.5mあったため、この柱状地盤
改良を採用することになりました。
これは、ミキシングプラントと呼ばれる機材。
一袋で1tの重さがあるこの固化材を、クレーンで持ち上げて移動させ、
ミキシングプラントへ流し込み、
水と混ぜて、練っていきます。
そして、ポイントごとに、このように青い×マークをつけ、
柱状機という機材で、地面に垂直に穴を掘り下げ、それと同時にミキシング
プラントで練ったセメントを穴の中に流し込みます。
写真は、柱状機の先端。
小さな穴が開いていて、そこからセメントが流れ出る仕組み。
最大6mまで掘り下げられる柱状機を使って、地盤を強化するポイントは計29ケ所。
今回は、14トン分の固化材が、地盤改良工事で使われる予定です。
2007年11月26日
晩秋の地鎮祭
しばらく続いていた寒さも緩み、きれいに晴れ渡った日曜日

川中島で新築を予定しているIさまの家の地鎮祭が執り行われました。
神主のトミオカさんが四方の神さまに切幣を撒いて、祓い清めます。
それを終えると、玉串奉奠(たまぐしほうてん)。
神主さんから受け取った玉串(榊)をうやうやしく捧げ、神さまに工事の無事と、
建てる家のご加護を願います。
お施主のIさま、それから奥さま。
幼い息子さんと娘さんは、それぞれ、お父さんとお母さんにお祈りの仕方を
教わりながら、玉串を奉納しています。
初めての儀礼的なお祈りに、こころなしか気恥ずかしそうな様子です。
そしてさいごに、奥さまのご両親が玉串を神さまに捧げます。
青空の下、みんなで笑顔で記念撮影。
こちらのIさまの家は、これからしばらくして基礎工事がはじまり、
来春の完成を目指す予定です

2007年11月22日
ソプラノ歌手金子みゆきさんリサイタルのご案内
今朝9時。
社員の多くの人たちが暖かい九州へ向けて旅立ちました。
松本空港から福岡空港へ飛び、それからバスで由布院などを周る
2泊3日社員旅行。
それゆえ会社内は、いつもよりもだいぶひっそりとしています...
さて、今日は1ヵ月後に長野市で行われるクリスマスコンサートのお知らせです↓↓

昨年当社で建替工事をさせたいただいた、ソプラノ歌手金子みゆきさんの
リサイタルが予定されています。
新築祝いのパーティーでも、何曲か歌ってくださったそうで、
その歌声に、営業アライさんもずいぶんと感激したとのこと。
クリスマスにぴったりのコンサート。
みなさんもぜひ足を運んで、美しい歌声に耳を傾けてください☆
会場/若里市民文化ホール(TEL 026-2223-2223)
日時/2007年12月22日(土) 開場5:30pm 開演6:00pm
入場料/¥2000(全自由席)
お問合せ/026-233-0890(金子)・w-konzert@jcom.home.ne.jp
電子チケットぴあ予約番号/
0570-02-9999 (クラシック専用)0570-02-9990
◎曲目ラインナップ◎
この道・赤とんぼ・ペチカ・雪の降る町を・歌の翼・ローレライ・野バラ・千の風になって・
涙そうそう・君をのせて(天空の城ラピュタ)・赤鼻のトナカイ・ホワイトクリスマス・
アヴェマリア・忘れん坊のサンタ苦労す ほか (曲目は変更になる場合もあります)
◎金子みゆきさんのプロフィール◎
長野市出身。長野県立西高等学校卒業。東京音楽大学卒業、
同大学研究科オペラコース修了。
読売新人演奏会、東京文化会館新人推薦演奏会、日本演奏会
連盟推薦新人コンサート等に出演。
1989年、DAAD西ドイツ給費留学生として留学。シュトゥットガルト
国立音楽大学大学院、リートクラス、および、オペラコース修了後、
ドイツ各地の劇場で舞台に立つ傍ら、宗教曲のソリストとしても多数の
コンサートに出演。
2002年12月に帰国。現在、合唱団コールはなみずき常任指揮者、
東京音楽大学付属高校非常勤講師。
社員の多くの人たちが暖かい九州へ向けて旅立ちました。
松本空港から福岡空港へ飛び、それからバスで由布院などを周る
2泊3日社員旅行。
それゆえ会社内は、いつもよりもだいぶひっそりとしています...
さて、今日は1ヵ月後に長野市で行われるクリスマスコンサートのお知らせです↓↓
昨年当社で建替工事をさせたいただいた、ソプラノ歌手金子みゆきさんの
リサイタルが予定されています。
新築祝いのパーティーでも、何曲か歌ってくださったそうで、
その歌声に、営業アライさんもずいぶんと感激したとのこと。
クリスマスにぴったりのコンサート。
みなさんもぜひ足を運んで、美しい歌声に耳を傾けてください☆
会場/若里市民文化ホール(TEL 026-2223-2223)
日時/2007年12月22日(土) 開場5:30pm 開演6:00pm
入場料/¥2000(全自由席)
お問合せ/026-233-0890(金子)・w-konzert@jcom.home.ne.jp
電子チケットぴあ予約番号/
0570-02-9999 (クラシック専用)0570-02-9990
◎曲目ラインナップ◎
この道・赤とんぼ・ペチカ・雪の降る町を・歌の翼・ローレライ・野バラ・千の風になって・
涙そうそう・君をのせて(天空の城ラピュタ)・赤鼻のトナカイ・ホワイトクリスマス・
アヴェマリア・忘れん坊のサンタ苦労す ほか (曲目は変更になる場合もあります)
◎金子みゆきさんのプロフィール◎
長野市出身。長野県立西高等学校卒業。東京音楽大学卒業、
同大学研究科オペラコース修了。
読売新人演奏会、東京文化会館新人推薦演奏会、日本演奏会
連盟推薦新人コンサート等に出演。
1989年、DAAD西ドイツ給費留学生として留学。シュトゥットガルト
国立音楽大学大学院、リートクラス、および、オペラコース修了後、
ドイツ各地の劇場で舞台に立つ傍ら、宗教曲のソリストとしても多数の
コンサートに出演。
2002年12月に帰国。現在、合唱団コールはなみずき常任指揮者、
東京音楽大学付属高校非常勤講師。
2007年11月21日
2週間前→今日
11月7日(水)
南高田で工事が進む2世帯住宅、Tさまの家。
これは2週間前の様子で、この日は屋根屋さんが3人で瓦を施工し、
大工のヤマグチさんと、マーくんは、床組みを敷く作業をし、
コウメイさんは、捨て鴨居を取り付けていました。
11月21日(水)
そしてこちらが、それから2週間後の今日の現場の様子です。
1階にはすでに樹脂サッシがはめ込まれ、
床は、根太の間に断熱材が施工されている部分もありました。
大工さんたちは、今日はみなさん2階で作業中。
「顔は写すなよ、ファンが増えちゃって困るから」などといいつつ、こっちに顔を
向けているのでばっちし写りこんでいます。。
そのヤマグチさんは、外壁の下地を施工中。2階のベランダになる部分です。
顔写すな、といいつつ、なぜかカメラのほうに顔を...
この部分の外壁下地は、屋根の勾配に合わせて斜めになっています。
2階はこれからサッシが入れられます。今はまだ窓枠があるだけ。
2007年11月20日
初冬のスケッチ
まだ陽も昇りきらない、朝6時半。
吉田で完成間近のIさまの家の近くの公園に、デジカメ片手にのっそり
現れた男の影...
それは、当社の営業アライさん。
アライメモによると、今日はIさまの家の引っ越しのお手伝い、明日は
解体前にお預かりする荷物を運ぶお手伝いと多忙で、"芸術"作品を
撮影する時間がとれないため、早朝出勤してここ、辰巳池に"スケッチ"
しに来たそう。
"自称芸術作品"への執念は、なみなみならぬものがあります...
ちなみに向こう岸にぽつぽつ見える白い点は、就寝中のシラサギたち。
水際に近寄ったアライさん。
「人に慣れた水鳥で、えさをやる真似をすると、寄ってきました」(アライメモより)
...なんてひどい人だ...
そして心をもてあそばれたことを悟った鳥たちはこぞって、さっさと
元の生活へ戻って行きました。
「なんだよアイツ」「期待させてさ」「ひどいよ」と、かれらの背中が
語っているように、見えなくもありません。
ブレまくりの写真ではありますが、小さな草の葉や枯葉にシャリっとした
霜が降りているのはわかります。
早くも最低気温が0℃を下回る日が出てきました。
今日は、日中、会社のすぐ近くで家屋が全焼する火災も発生しています。
暖房器具や家電製品からの出火には、くれぐれも気をつけたいものです。。
2007年11月19日
秋晴れ土曜日の地鎮祭
きれい晴れた小春日和で、冬はまだすこし先だと思っていた先週の土曜日。
若宮にて新築予定の、Mさまの家の地鎮祭が執り行われました。
列席者は、Mさま家族と、親御さん、設計のワダさんと代理人のナガオさん。
この日も、戸隠から神主のトミオカさんにおいでいただき、祭事を司っていただきました。
四方に宿る神様を鎮めるため、細かく切った紙である切幣(きりぬさ)を
撒き散らします。
その様子を、後からみんなで見守っています。
お施主さま家族、工事関係者がそれぞれ、榊を神様に奉納する玉串奉奠。
まずは施主のMさまからです。
つづいて、奥さまと子どもさんたち。
幼い娘さんも、お母さんといっしょになむなむしています。かわいらしい。。
親御さんも玉串を捧げ、これから始まる工事の安全や、ここに住まう家族への
ご加護を祈られました。
さいごにお施主さまご一家と、神主トミオカさんで
記念撮影です(さりげなく遠近法?)。
こちらのMさまの家は、来春の完成を目指し
これから工事がはじまります

ちなみに
「今回は、除草剤を撒いたこともあって花が見当たらなかったため、花シリーズは無しで」
との営業アライさんにからのアライメモが...
雪も降ったことだし、花を撮ることに執念を燃やすアライさんにとっては
これから厳しい季節になってきます。
さてさて、どんな工夫(反則技?)が飛び出すことか。。
2007年11月16日
パテをかう
千曲市で2棟同時に新築中のSさまの家。
夏の間、営業アライさんお気に入りの"かかし"が見張っていた田んぼは、
いつしかグラジオラス畑に変わっていました...
ご長男の家の方では、職人さんがパテをかっていました。
このドロっとしたものが、パテ。
クロスの下地であるプラスターボードを施工する際にできてしまうビスや、
継ぎ目の凹凸を、このパテで埋めて平らにし、それからクロスを張るのです。
玄関ホールも、
キッチンも、その向こうの部屋も、クロスを張る予定の壁にはすべて、
パテがかわれます。
1週間くらい後には、クロスがすべて張り終えられるようです。
この赤い実は...
営業アライさん、晩秋を演出しようと撮ってきたのでしょうが、これはちょっと、
美しいというかなんというか。
一方、ご長男の家のすぐ隣で工事が進む、ご次男の家。
こちらでは、大工のアライさんが造作作業中です。
2007年11月14日
山茶花まぶしい片づけ風景
長野市稲里町にて、建て替えを予定されているSさまの家では、
今日から既存住宅の解体工事がはじまりました。
お仕事のお休みをとって、一日現場にいらっしゃるという施主のSさまに
うかがったところ、築年数は「45、6年くらいかな...」とのこと。
一部で、手ばらしがはじまった現場では、同時に家の中の片づけが
進んでいました。
トラックの荷台や、庭先のコンテナにめいっぱいの不用品。。
「想像以上に物があった」と、Sさまは数十年かけて蓄えていた荷物の
多さに驚かれている様子でした。
「今日の"芸術"(←自分で撮ってきた写真のこと)みた?」と営業アライさん。
いつものアライメモには「今日は"椿"をとりこんでみました...」なんて
書かれていたけれど、この時期に椿はないでしょう、ということで、
これは山茶花(さざんか)。ピンク色がずいぶん鮮やかです。
「(Sさまの家が)完成する時は、紫陽花を一緒に撮る予定です」by 営業アライ
2007年11月13日
昭和49年...
(文・写真/営業アライ)
ここ、篠ノ井のOさまの家が建てられたのは、
山手線の初乗りが30円、タバコ一箱100円、
中村雅俊の『ふれあい』がヒットしていた年...昭和49年。
今回、大幅なリフォームをご計画され、今日解体工事がはじまりました。
当時の「土壁」の家の間仕切りを取り払い、広々としたスペースを造る予定です。
リニューアル後をお楽しみに!!
2007年11月12日
格天井とシステムキッチン組立ての様子
銀色に輝くススキの穂が風で揺れる土手の近く...
(またしても撮影のためだけに遠征した営業アライさん...まったく。。)
篠ノ井で工事がすすむ分離型2世帯住宅のTさまの家では、広い
玄関ホールの天井の施工が行なわれていました。
このような正方形の升目で構成される天井の造作を、格天井(ごうてんじょう)
と呼びます。
格天井は、平安時代の寝殿造りではじめて用いられて以降、寺院建築や
書院建築の客殿などに使われてきた格式高い天井形式。
重厚で荘厳な印象を与える、というのが特徴です。
職人さんが、正方形の格子の中にはめこむ鏡板を切っています。
昔は無垢板が使われていましたが、今は種類が多くて安価、割れや反りが少ない
などの理由で化粧合板が多用されます。
切った材をはめこんで、
釘で止めて施工します。
「一枚一枚、柄を見ながらの作業で、たいへん」と職人さん。
精度が要求され、手間のかかる作業ですが、そこから生まれた空間には
高級感が漂います。
一方、親世帯のキッチンでは、設備屋のハセガワさんがシステムキッチンの
組立て作業をしていました。
箱清水で建築していた2世帯住宅でも、キッチン組立てを担当していた
ハセガワさん、「この家は、柱がとんでもなく太いですねえ」と驚き顔
だったそう。。
シックなブラウンを基調としたシステムキッチン。できあがりに乞うご期待です

2007年11月09日
上棟しました!
昨日の川合新田、Kさまの家の上棟風景のつづき。
これは、お昼過ぎの現場の様子です。2F部分が徐々に組みあがっていきます。
位置の高いところも、クレーンで吊り上げられた部材をひとつひとつ慎重にはめます。
あの高くて細い足場の上に立って作業している大工さんたち。
もともと高いところが平気なのか、怖さを克服したのか、気になるところです。。
午後5時前、日が傾いてあたりはずいぶん薄暗くなってきました。
ヤマナカ大工さんが左足をのっけている材、これが屋根の一番上にのせる
棟木という材。
この棟木を上げる、ということが「上棟」といわれる所以です。
施主のKさま家族もいらっしゃって、上棟式です。
お施主さまのお子さん。
頭のてっぺんにちょこんと乗っているゴマちゃん(?)がよく似合っていて
かわいらしい。。
お施主さま、大工さん、わたしたちみんなで上棟の無事を感謝し、
これから先の工事の安全を祈願

来春の完成を目指し、これから工事が進められます。
2007年11月08日
川合新田で上棟しています
朝からきれいな秋晴れの空の下、川合新田で新築予定のKさまの家の
上棟が行なわれています。
まだお若いけれど、腕が立つ大工さんです。
写真真ん中で梁材の下に端材を差し込んでいるのが、K邸の現場代理人マチダさん。
大工のコウメイさんとシゲオさんが大きな梁材の両端を支え、
マチダさんが紐で結わえて、
タケダさんが操縦するクレーンで持ち上げ、
所定の位置へ運び、
6名の大工さんとマチダさんが、力を合わせて大きな梁を慎重にはめ込みます。
あたりには、時折、掛け矢(木槌)が材木を打ちつける心地の良い音が響いています。
今日の夕方には、棟木が上がる予定です

2007年11月02日
完成住宅見学会を開催します
1週間ほど前にもお知らせしましたが、
この週末11月3日(土)・4日(日)の2日間
こちらのIさまの家(2世帯住宅)で完成住宅見学会を開催いたします!
詳しくは明日11月3日付週刊長野掲載広告をご覧ください。
完成見学会を控え、昨日はタイル屋さんが玄関ポーチの床タイルを張っていました。
完成まであとわずかです

中は、クリーニングを待つばかり。
1F親世帯のシステムキッチンは、山吹色に近い黄色で明るい雰囲気。
ダイニングキッチンとつながるリビング。奥の明るいスペースは、サンルームです。
2F若夫婦世帯、リビングからダイニングキッチン方向を望んだ様子。
縦長の広い開口(窓)が特徴的です。
LDKを広いひとつの空間にするお宅も増えていますが、I邸では、ダイニングと
リビングの間に間仕切り戸を設置して、空間の使い方に柔軟性をもたせています。
このような間仕切戸だと、光を透過するため圧迫感も少なく、デザイン的にもおしゃれ。
完成見学会会場のI邸は、善光寺や城山公園のすぐ近く。
美術館や動物園や公園ピクニックのついでに、ぜひ会場へお立ち寄りください

2007年11月01日
火山灰からできた"薩摩中霧島壁"
現場に行くと、大きな猫に遭遇しました。
歌舞伎役者の隈取のように、黒くくっきりと縁取られた目元に凄みが。。
そしてものすごく、警戒しています...
それはさておき、こちらは、長野市吉田で建築中のIさまの家。
中では左官屋さんが、壁材を塗っていました。
(写真は、ふちに張ったマスキングテープをはがしているところ)
家づくりで使う素材にとことんこだわっておられる、施主のIさまご家族。
左官屋さんが塗っていた壁材はこれ、薩摩中霧島壁です。
この内装材の原材料は、鹿児島県の霧島山麓の火山灰・白州(シラス)。
製造販売元である株式会社高千穂さんのHPにある説明によると、
これは100%自然素材で、調湿性や消臭性、吸音性や耐火性などに
優れているのだそう。
当社のお客様でも、お子様がアレルギーをお持ちという家や、健康や
環境への関心が高い方が積極的に採用されるケースが多い内装材です。
作業中の左官屋さんの傍らには、いろいろな種類のコテが置かれていました。
これはその一部。
部位や工程によって、すべてを使い分けながら壁材を塗っていくそうです。
I邸のほとんどの内装は、上の写真のように、白色の中霧島壁塗りで
コテむらを残した仕上げ。
一方和室の壁面だけは、下写真のような茶色の中霧島壁を選び、
刷毛目をつけて仕上げてあります。
「若い人はコテむらを"味だ"って言うけど、年配の人はただ職人が下手な
だけだと言って嫌がるよ」と、左官屋さん。
2Fはすべて、壁塗り作業が終わっていました。
こうみると、杉板の腰壁と中霧島壁塗りの壁は、同じ自然素材のためか、
色や質感の相性がとても良いように感じられます。
ちなみにI さまの家の大工工事を終えたハラダさんとハラヤマさんは、今は会社の
作業場で次に造るUさまの家の墨つけ&刻み作業中です。