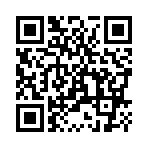2017年04月14日
長野市稲田で地鎮祭が執り行われました。
先日、長野市稲田のTさんのお住いの
地鎮祭が執り行われました
設計は下崎建築設計事務所さん、萌建築設計工房さんです。

一般的に地鎮祭(じちんさい)と呼んでいるこの祭りは
大和詞では『とこしずめのまつり』と読みます。
最も古い記録が、西暦690年頃(飛鳥時代)持統天皇期に、
藤原京の造営に先立って「鎮め祭らしむ儀式」が行われていたと
日本書紀に記されています !
!

実際に地鎮祭が建築儀礼として認められ
広く普及していったのは、一般庶民が家へのこだわりを持ち始めた
江戸時代後半になってからと考えられています。
最近は地鎮祭を行わないという所もあるそうですが、
1300年以上の歴史があり、古来から受け継がれてきた重要なお祭りです

神主さんが四隅と中央は祓い清め
災いが起きないように願います。

神主さんから参列者ひとりひとりに玉串が手渡されます。


篳篥(ひちりき)の音が響く中
工事の安全を祈り、玉串を捧げます。

最後に神前に供えられた御神酒を頂き、
無事に地鎮祭が終了しました。
これからTさんのお住いの工事が始まります。
どうぞ宜しくお願いいたします
地鎮祭が執り行われました

設計は下崎建築設計事務所さん、萌建築設計工房さんです。
一般的に地鎮祭(じちんさい)と呼んでいるこの祭りは
大和詞では『とこしずめのまつり』と読みます。
最も古い記録が、西暦690年頃(飛鳥時代)持統天皇期に、
藤原京の造営に先立って「鎮め祭らしむ儀式」が行われていたと
日本書紀に記されています
 !
!実際に地鎮祭が建築儀礼として認められ
広く普及していったのは、一般庶民が家へのこだわりを持ち始めた
江戸時代後半になってからと考えられています。
最近は地鎮祭を行わないという所もあるそうですが、
1300年以上の歴史があり、古来から受け継がれてきた重要なお祭りです

神主さんが四隅と中央は祓い清め
災いが起きないように願います。
神主さんから参列者ひとりひとりに玉串が手渡されます。
篳篥(ひちりき)の音が響く中
工事の安全を祈り、玉串を捧げます。
最後に神前に供えられた御神酒を頂き、
無事に地鎮祭が終了しました。
これからTさんのお住いの工事が始まります。
どうぞ宜しくお願いいたします

Posted by カマクラさん at 13:24│Comments(0)
│◇稲田のT様邸