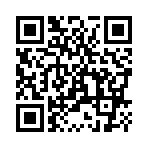2007年10月16日
そば処『藤木庵』さま、地鎮祭(とこしずめのみまつり)
朝9時半より、善光寺の近くにある藤木庵さんの地鎮祭が行われました。
地鎮祭は、正しくは"とこしずめのみまつり"と云われるのだそうで、長野神社庁
発行の『一人奉仕の地鎮祭』によると、持統天皇の御代(690年)にはすでに
この祭事の記録があるようです。
最近は、地鎮祭を省略する建設会社も多いと聞きますが、鎌倉材木店では
家を建てるにあたって大切なことと考え、お施主様とともに執り行っています。
地鎮祭のはじまり。
戸隠神社の神主トミオカさんが、手元の太鼓を打ち、祓詞(はらいのことば)を
奏上します。
そして大麻(おおぬさ)で、すべてを祓い清めます。
つづいて神籬(ひもろぎ:場を囲む縄にぶらさがっている白い紙)に神様を
お招きする儀式である"降神"。
神主さんが「オーー」という、よく響く一声をあげます。
この声は警蹕(けいひつ)といい、もともとは天皇のお出ましや高い身分の
人が通る際、人々が失礼なことをしないようにと先払いが声をかけて注意し、
警戒するというのが本来の意味で、このことが神事に於いても取り上げられ
るようになったのだそうです。
国土守護神である大地主神(おおとこぬしのかみ)と、この土地の守護神である
産土大神(うぶすなのおおかみ)に祝詞をあげたら、清祓散供(きよはらいのさんく)
の儀へ。土地の四隅の神々を鎮めるために、切幣(きりぬさ)をまき、祓い清めます。
普段の地鎮祭と少しちがうのが、これらの農具を模した道具を使って行う儀式。
本式の地鎮祭では執り行うのですが、一般住宅の地鎮祭では省略させていた
だいている部分です。
農具はそれぞれ白木で作られ、忌鎌(いみかま)・忌鍬(いみくわ)・忌鋤
(いみすき)と呼ばれるそうです。
まず刈初(かりぞめ)の儀。
設計会社である㈱アーキプランの所長さんが、「えいっ、えいっ、えいっ」といい
ながら、こんもり盛られた砂の山"斎砂(いみすな)"のてっぺんに挿された榊を、
鎌で刈り取ります。
つぎに、鍬入(くわいれ)の儀を行います。
お施主様である藤木庵さんが、声をかけながら、忌鍬で斎砂を崩します。
そのつぎに、鋤入(すきいれ)の儀。
施工会社である鎌倉材木店、会長が「えいっ、えいっ、えいつ」とさらに砂を崩します。
神主さんが、崩された斎砂の上に鎮め物を
置き、埋納します。
そのあとが、玉串奉奠(たまぐしほうてん)。
工事の無事と安全を祈って、建設に関わる人々が順番に玉串(榊の枝に
紙垂と幣をつけたもの)を神様に奉納します。
神籬(ひもろぎ)にお招きした神様にお帰りいただく儀式の"昇神"を終えたら、
御神酒をいただきながら"直会(なおらい)"。全員で地鎮祭をお祝いです。
㈱アーキプランの方々、そして鎌倉材木店の
面々、神主さんもいっしょに記念撮影。
来年3月の完成をめざし、これから建築工事が
進められていきます。